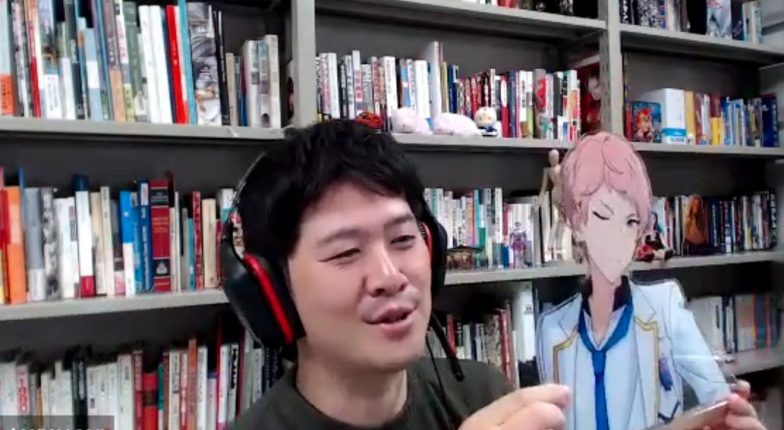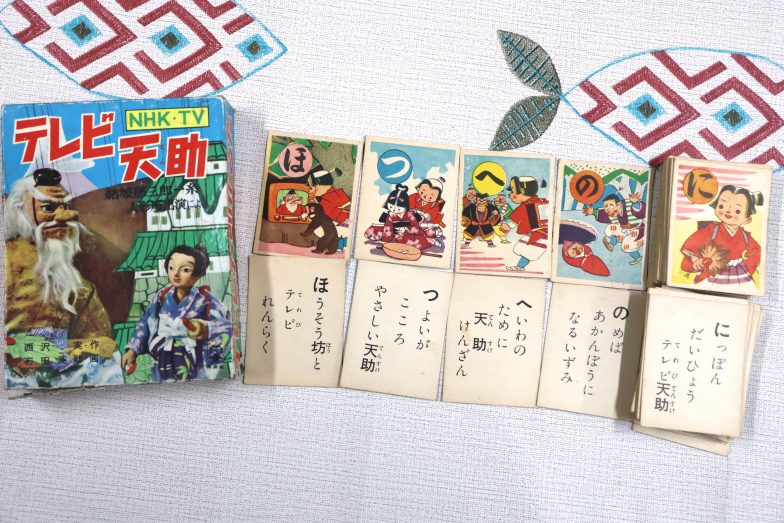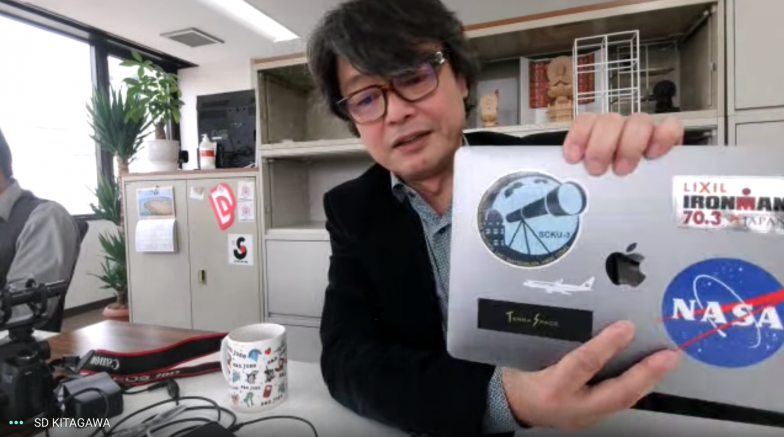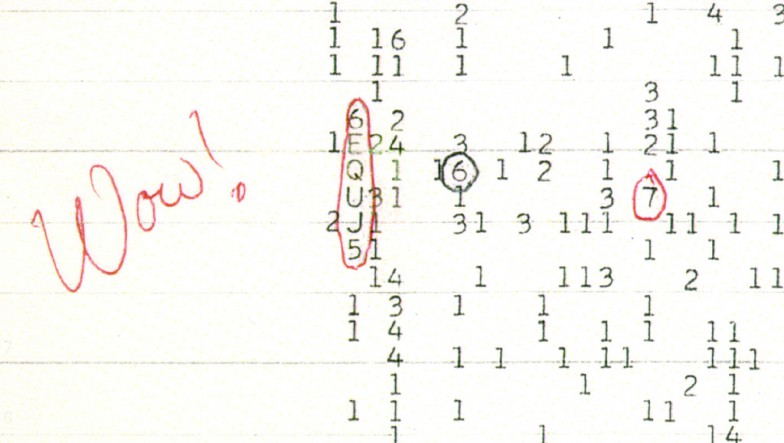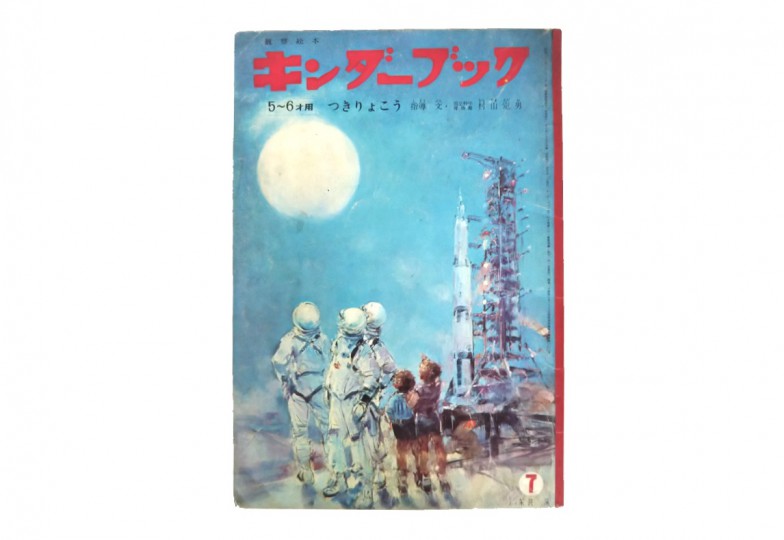植物図鑑(2):土をつくり、森を育てる。身近な植物・コケの美しさと生態系で果たす大きな役割を学ぼう
2025年6月12日 / 大学の知をのぞく, この研究がスゴい!
地上のあらゆる場所に進出し、多種多様な戦略によって繁栄してきた植物たち。連載企画「植物図鑑」は、そんな植物たちのめくるめく生き様を、その道の研究者に案内してもらうコーナーです。
第2回は、「コケ×大石善隆先生(福井県立大学 恐竜学部 教授)」。身近な植物でありながら実は地球環境にも大きな役割を果たしているコケの秘密と魅力、最新の研究について伺いました。(編集部)
根のない植物、コケの不思議な生態
下を向いて歩いてみれば、木にも石にも、コンクリート塀にもひっそりと生えている「コケ」。町でも山でもよく見かけるものの、筆者がコケに持っているイメージは「地面に生えている植物みたいなもの」という漠然としたものでしかない。科学的に説明すると、コケはどういう生き物なのだろう?
「コケは、水中から初めて陸にあがった植物の特徴を強く残している分類群で、正式な名前を蘚苔(せんたい)類といいます。祖先は約4億5000万年以上前に生まれたとされ、水中に生える藻類と比べると、発生直後の幼い植物を乾燥から守る仕組みが発達しているのが特徴です。地面に生えているように見えますが、実際には『仮根』という根っこみたいなもので張り付いてるだけ。維管束もないので、水や栄養分を体全体に運ぶシステムはありません。
ちなみに地衣類の一部にもコケと呼ばれるものがありますが、あれは植物というより菌類と藻類の共生体です。私の専門は完全に植物のコケです」

地衣類のコケ(左:ウメノキゴケ)と、植物のコケ(右:ミドリゼニゴケ)
なんとなく見た目の雰囲気が違うと思ってはいたけれど、植物のコケと地衣類のコケはまったく別の生き物だったのか。根も維管束もないというのは、他の植物と違ったコケの大きな特徴だ。水や栄養はどうやってとっているのだろう。
「コケは体全体から水や栄養分を吸収しています。雨や霧などから直接吸収するので、土のない木の幹や石の上にも生育できるわけです。雨や霧からとれる栄養は限られていますが、コケは非常に小さい植物なのでそれでもやっていけるし、成長もそこまで早くありません。育つために土から大量の栄養分を吸収しなければいけない樹木などに比べると、少ない栄養で生きられることもコケの特徴の1つです」
まるで霞を食べて生きる仙人のような生き様だ。雨や霧から栄養をとるという話の通り、ジメッとした場所に生えるイメージがあるけれど、やはり湿気のある環境が好きなのだろうか。それに、少ない栄養では繁殖するのも難しいのでは?
「一般的にいうと、乾燥しすぎはだめだし、かといってビシャビシャでもダメです。朝露や霧で適度にしっとり濡れるくらいの環境を好みます。とはいえ種類によってそれなりにさまざまで、乾燥に強いコケや、水の中で生育するコケもいます。日光についても、直射日光は当たらないけれど、光合成をしっかりできるぐらいの明るさは必要です。なので、環境条件としてはけっこう厳しいかもしれません。
繁殖については、ほとんどの種が2つの殖え方を持っています。1つは体の一部がちぎれて殖えていくという方法。もう1つは胞子です。ただ、胞子は小さくて遠くまで散布できるという利点はありますが、種ほど乾燥に強くありません。さらにメスとオスが出会って胞子体を作る必要があるので、ちぎれて殖えるやり方に頼ることが多いです。あとは、イモのツルにつくムカゴってありますよね。ああいうムカゴに似た小さなものを作って殖えるコケもいます」



コケには蘚(せん)類、苔(たい)類、ツノゴケ類という3つの分類がある。これらは胞子体が大きく異なる。なお、胞子体がないときは見た目が紛らわしいものもあるが「慣れるとすぐにわかります」と大石先生。
写真は上から、
ハリガネゴケ(蘚類)
ホソバミズゼニゴケ(苔類)
ニワツノゴケ(ツノゴケ類)
観察すると楽しい!コケの楽しみ方入門
ここからは、先生ご自身についても少しお話をうかがった。著書やブログからもコケへの愛情が感じられる大石先生だが、初めてコケに興味を持ったのはいつだったのだろう。
「いつとはっきり答えるのは難しいかもしれません。静岡県の出身で、今は都市化が進んでいますけれども、典型的な里山のある環境で育ちました。子どもの頃から植物だけじゃなくて小さな生き物に興味があって、昆虫を集めたり、魚を捕って飼ってみたりとか。
でも、昔からバラのような華やかな植物より、コケのような清楚で透明感のある植物が好きだったんです。そんな感じだったので大学では理学部を選びました」
大石先生が「清楚」と言い表しているように、コケには独特の美しさがある。筆者もインタビューの前に庭でコケを探してみたところ、色も形も驚くほどさまざまなコケが広がっていて、これまで野草や樹木にばかり注目していたのをもったいなく思ったほどだ。コケを観察する上で、必要な道具やコツはあるのだろうか。
「まず大事なのはしゃがみこむことです。家から一歩出てしゃがみこめばそこにコケがあって、いつもの目線では見えなかった小さな美しい世界が広がっています。この小さな感動を大切にすることが観察の第一歩かなと思います。道具としてはルーペがあると便利ですが、最近ではスマホのカメラもかなり発達していて、スマホでも結構いい写真が撮れますよ。
特に、雨上がりや朝露のおりている時間はコケの上に水滴がついていたりしてとてもきれいです。反対に、乾燥しているとくしゅっと縮んでしまいます。季節としては雨の多い梅雨時だったり雪国の春先だったり。春は新芽も出てきて見応えがあります」
梅雨の季節に合わせてルーペを持ち歩いておくと、待ち合わせなどの時間にも退屈することなくコケ観察を楽しめそうだ。身近に見られるコケにはどんな種類があるのだろう?
「都市部なら、道端のアスファルトやコンクリートにはギンゴケやホソウリゴケ、ハマキゴケなどがよく見られます。公園に行けば、ヤノウエノアカゴケ、タチゴケ、ハイゴケ、ゼニゴケなどが定番。これらは比較的どこでも見られる種類です。
でも、最初は種類にこだわらず、形や色の違いを楽しむだけでも十分面白いですよ。興味を持つことの始まりって、やっぱり美しさだと思います。美しいものは見てて楽しいですよね、まずはその美しさに触れることがポイントです」

エゾスナゴケ。北海道から九州まで分布し、街中でも見られる

苔庭にもよく利用されるヒノキゴケ。別名イタチノシッポ
コケの美しさを楽しむといえば、コケ園芸というのも耳にしたことがある。「苔玉」「苔テラリウム」などの名前で売られているあれだ。大石先生も自宅で育てたりするのだろうか。
「出張が多いので家ではやっていないですが、栽培するのも面白いですね。他の植物のようにわかりやすく成長するわけではないですが、じっくり観察すると小さな変化があります。
コケの栽培は環境管理と、育てやすいコケを見つけることがポイントです。おすすめの種類はコツボゴケ。日向に生えるコケの方が育てやすいイメージがあるかと思いますが、瓶の中は湿度がこもりやすいので、湿った環境を好むコツボゴケのような種類の方が育てやすいです」
ちなみに観察や鑑賞以外の楽しみ方として、先生はコケを食べてみたことがあるとか。ふかふかと盛り上がる濃緑のコケは抹茶ケーキのようでおいしそうな気もするが、実際のお味の方は……?
「はい、キノコの研究室がキノコ鍋パーティをしていたのがうらやましくなって、コケを食べたことがあります。でもたいてい青臭かったり、えぐみがあったりでおいしくないです。ものすごくまずい。天ぷらで食べる人もいますが、無味のパセリのような感じ。
コケは食糧には向かないようです。小さくて花も咲かせない、おまけにまずくてコケにされがちなコケですが、その生態的意義は味の悪さを補って余りあるはず……と、コケの意義を明らかにしようとあらためて感じました」

ルーペでコケを観察する大石先生
「緑の地球」の立役者!生態系におけるコケの役割
研究のかたわら、苔庭にスポットを当てた『苔三昧 モコモコ・うるうる・寺めぐり』(岩波書店)を出版するなど、コケの文化についても造詣の深い大石先生。今、熱中している研究テーマについて聞いてみた。
「その時々で変わりますが、今一番興味を持っているのは、コケが生態系の中で果たしている役割についてです。先ほどお話ししたように、コケは根がなく体の表面から水や養分を吸収できるので、火山の噴火が起こった後の土がない環境でも生育できるんですね。
日本の溶岩台地でも、数年後にコケが生え、やがて枯れて腐ることで土壌がつくられ、数十年後に他の植物が入っていく様子が観察できます。一次遷移と呼ばれるプロセスです。何十年何百年という長いスケールで進むので、私たちがすべての過程を見ることはできないかもしれませんが、コケは森林形成における先駆者なんです」
言われてみれば、古代の地上に最初から栄養豊富な土などなかったはず。根のないコケの祖先が地上に進出することで土壌が生まれたということか。先生のお話でコケのすごさがだんだんわかってきたような気がする。それでは、最新の研究は?
「先行研究では、倒木の上に生えたコケが、他の木の種が発芽するための苗床のような役割を果たしていることは広く知られていました。コケが小さな木の種のゆりかごになっているということですね。
それだけでなく、最近の自分の研究では、コケが菌類・細菌類との相互作用を通して、倒木の分解にも関わっていることが分かりました。倒木の上にコケが生えることによって、その下に水分や栄養分が供給され、菌類や細菌類の活動が活発になる。その結果、窒素の移動や窒素固定などを通して倒木内の窒素濃度が高くなり、分解が促進されるようになる。このように、森林生態系の循環にコケが大きな影響を与えているという、新たな役割について最近発表しました。
コケは小さな植物ですが、実は森林への栄養塩の循環や、木の更新を助けたりしていて、生態系の中でいろいろな役割を担っています」

コケが豊かに繁茂する屋久島の森
土を作りだすだけでなく、他の生物とのタッグで窒素まで生み出しているとは……。生態系に欠かせない、まさに縁の下の力持ち。今度から森林を見る目が変わりそうだ。近年は環境破壊や気候変動が問題となっているが、コケとの関わりはどうなのだろう。
「コケは森林生態系を維持するだけでなく、地球規模の環境変化にいち早く警鐘を鳴らす役割も担っています。コケの体全体から水や栄養分を吸収するという特徴から、大気汚染物質なども吸収しやすいので、環境指標生物として広く利用されているんです。気温や湿度の変化にも敏感なので、例えば地球温暖化や都市化によるヒートアイランド現象の影響を早期に検出できます。
あとは越境大気汚染の指標としても使うこともできて、同位体などを利用すれば海外からやってきた大気汚染の影響も評価できます。森林の分断化や孤立化による環境変化についても、コケからいろんなことがわかります」
時間・空間・文化の3つの軸でコケ研究を進めたい
大石先生が在籍する福井県立大学では2025年に恐竜学部が開設され、大きな話題を呼んでいる。先生自身も4月から恐竜学部に所属しているが、恐竜や中生代の環境とコケの関係も研究の視野に入ってくるのだろうか?今後の研究の展望について聞いた。
「時間・空間・文化という3つの軸でコケを捉えていきたいです。時間軸では、古代にコケが地上に現れたことで地球環境がどう変化したのか、何億年という時間のスケールにいつか迫れたらいいなと思っています。空間軸では生態系の中での役割や、分布パターンを引き続き研究していきたいです。日本はコケが豊かな国なので、苔庭など独自の文化にも注目しています。国歌にもコケが登場しますし、時代ごとにさまざまな表象として描かれてきました。京都の苔庭は近年、環境変化の影響で危機に瀕していて、生物保全の問題とも関わっています。
恐竜学との関連は、直接的にはあまりないのかもしれません。恐竜の食性はあまり詳しくわかっていませんし、コケの化石もありますが量はそんなに見つかっていないですし。とはいえ、恐竜学部では、恐竜だけじゃなくて自然史系の学問を幅広く扱っています。自然史系の中には太古の昔から現在にかけての環境の変化であったり、太古の環境の復元であったり、今現在起こっている環境の変化と生態系の話であったりとさまざまなテーマが含まれます。
地質学や古生物学の研究者が多く集まっているので、その先生たちと交流することで、自分だけでは想像できないような新たな展開が生まれるんじゃないかと期待しています」
【植物図鑑:生態メモ】蘚苔類

水中から初めて陸にあがった植物の特徴を強く残している分類群。コケには蘚(せん)類、苔(たい)類、ツノゴケ類に分かれる。根や維管束はなく、水分や栄養を体全体に運ぶ能力はない。土壌のない場所にも生育でき、森林生態系の循環にとって欠かせない存在。