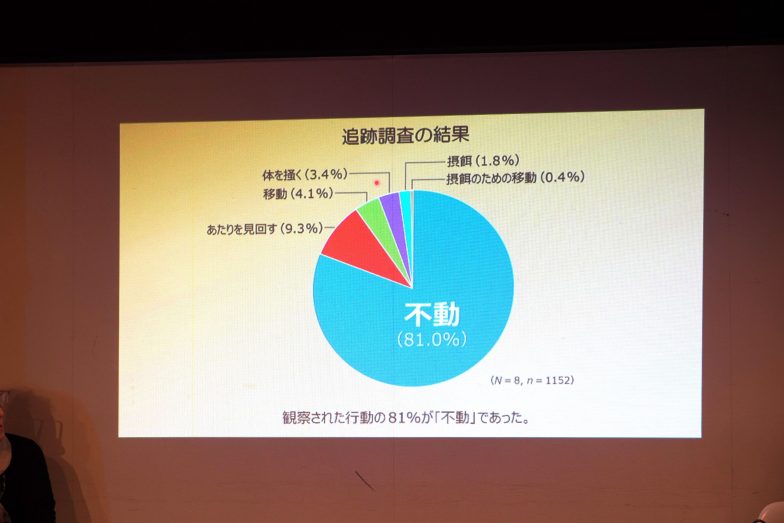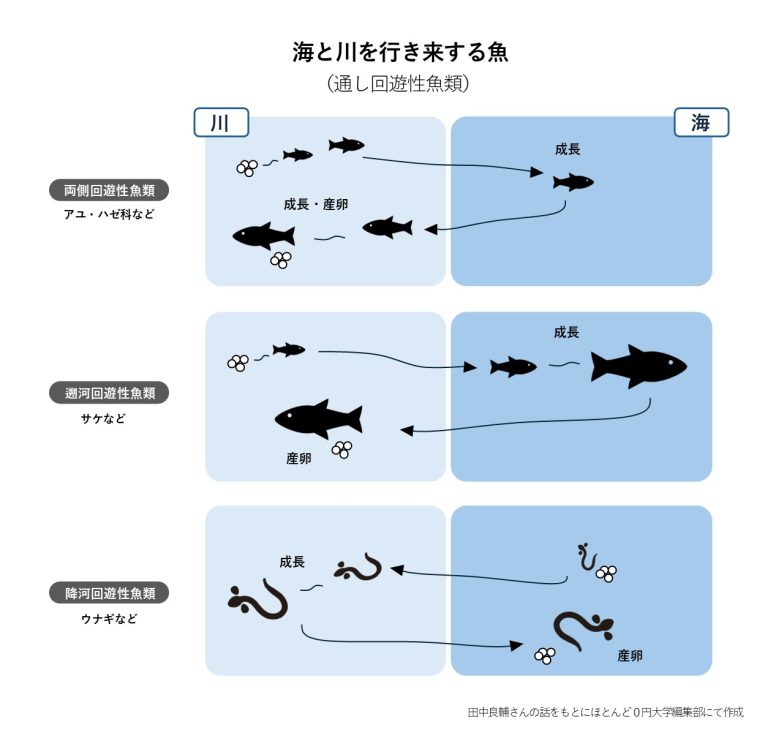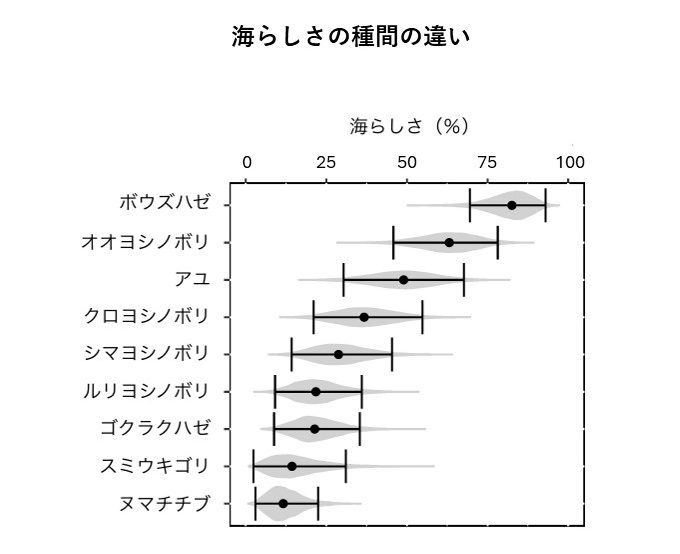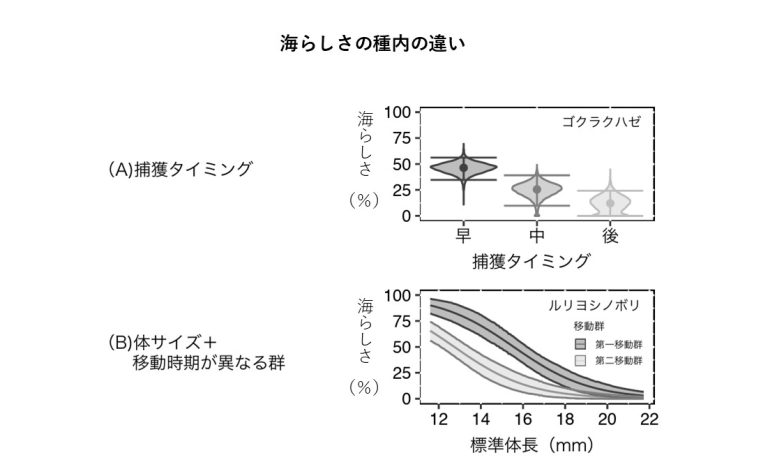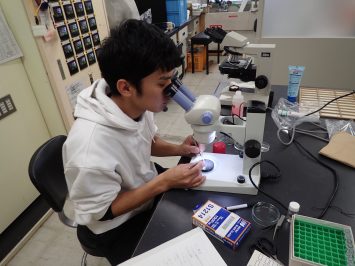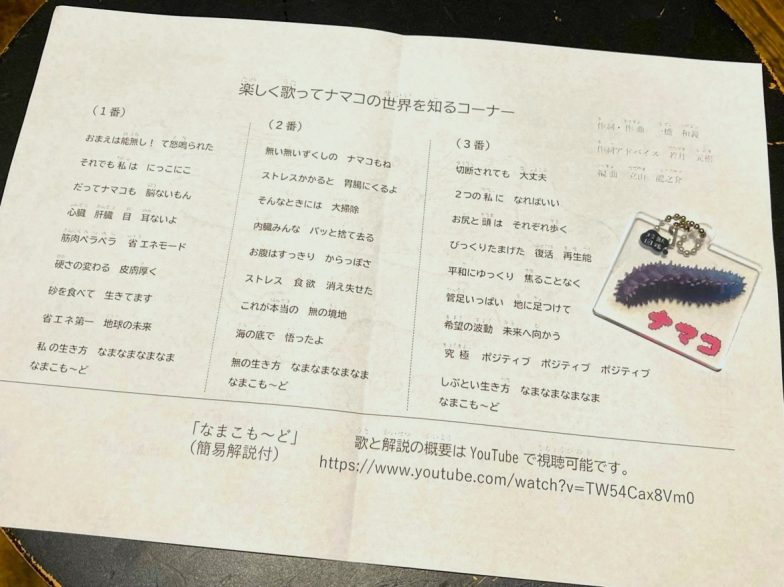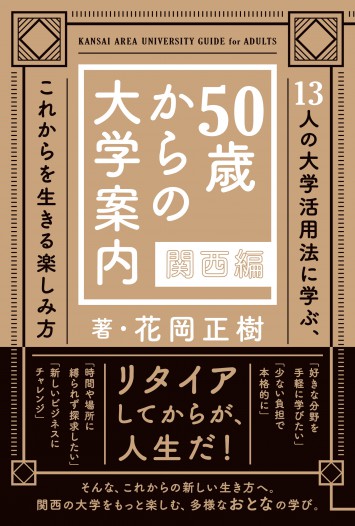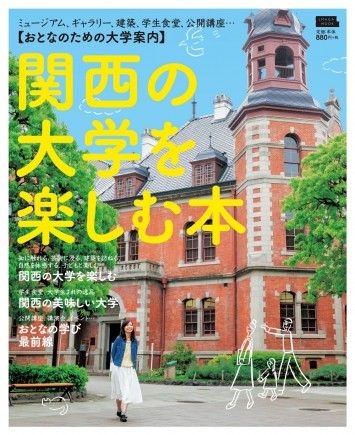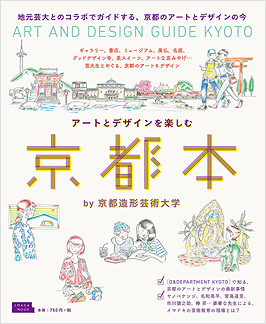野生動物と共存する社会とは? 立命館大学の桜井良先生に聞いた、野生動物被害への人間目線のアプローチ
2026年2月26日 / 大学の知をのぞく, この研究がスゴい!
2025年は、かつてないくらいクマ出没による人身被害のニュースが世間を騒がせた年だった。一方、あまりニュースにはならないものの、シカやイノシシといったクマ以外の動物も、農作物を食害するということで、毎年数十万頭が駆除されている。人間と動物、同じ日本列島に住む者同士、うまく折り合いをつけて生きていきたいものだと、一介の動物好きとしては思うのだが……。そんな気持ちに希望として映るのが、立命館大学・桜井良先生の研究だ。アメリカ発の「Human Dimensions(ヒューマン・ディメンション)」というアプローチをとっかかりとして、野生動物とのあるべき関わり方について聞いてきた。

お話を伺った桜井良先生
アメリカ発の概念「Human Dimensions」とは?
桜井先生の研究のキーワードである「Human Dimensions(ヒューマン・ディメンション)」という言葉は、どういう意味なのでしょうか?
「正しくは『Human Dimensions of Wildlife Management』といって、日本語では『野生動物管理における社会的側面』となります。つまり野生動物と付き合っていく上で、人間社会の側がなすべきことの研究ということになります。
野生動物の研究というと、生態学や獣医学といった、野生動物そのものを研究することが多いです。ただそれだけだと、野生動物と人間社会との間に起きる問題が解決できないということで、社会科学的なアプローチとして1970年代からアメリカで発展してきた分野がHuman Dimensionsです。
Human Dimensionsが活用されたわかりやすい事例としては、生態系再生のために実施されたオオカミ再導入が挙げられます。アメリカでもシカの増えすぎによる生態系の劣化が問題になっていて、そのための対策として絶滅したオオカミをカナダから再導入することで生態系を回復させようとしたんです」

増えすぎたシカの被害を軽減するためオオカミが再導入された場所のひとつ、イエローストーン国立公園(提供:写真AC)
オオカミの放獣!日本でもときどき議論にはなりますが、アメリカではすでに実行していたんですね。
「社会的にもインパクトのある取り組みだったと思います。畜産業の従事者は反対しますし、これは人間の側の合意形成と政策決定がとても難しい問題です。だからこそHuman Dimensionsの手法がとくに役立った事例であると言われています。イエロースートン国立公園の再導入に先んじてミシガン州で1970年代にオオカミが放された際は、その後、何者かによってオオカミが殺されて、いなくなってしまったということがあります。
つまり、最初はアメリカもあまり住民の意識を気にせずに、生態学的な合理性だけにもとづいてトップダウンで政策決定をしていたのですが、失敗して、政策決定・実施のアプローチを変える必要に迫られたのです」
そこでHuman Dimensionsの概念が重要になってくるということですね。具体的にはどういうことをするんでしょうか?
「まず地域住民の意識調査を行って、誰がどのような理由で反対しているのかをしっかりと理解した上で、普及啓発のためのコミュニケーションやディスカッションをする場が設けられました。そうした場で行政、研究者、そして反対する関係者が何度も顔を合わせて、全員が完全に賛成することはおそらくあり得なかったと思うんですけど、少しでも理解を得たり、あるいは被害が出た時の補償金などについて細部を調整していくことで、時間をかけて合意にたどり着いたとされています」
人間社会の側がおもなフィールドということなんですね。桜井先生の研究も、これと同じようなことを行っているのですか?
「関係者の意識調査、そして普及啓発のためのコミュニケーションとその効果測定というところは同じですが、もう一つ重要な要素にメディア分析があります。メディアというのは我々の意識や行動にものすごく大きな影響を与えるので、問題についてどういう報道がなされているのかを分析することはとても大切です。
意識調査、コミュニケーション、そしてメディア分析の三つを柱にして研究を進めています」
情報化社会が、問題をいっそう複雑にする
野生動物と人間社会の軋轢として、今日本で一番問題になっているのは、やはりクマのことでしょうか。報道を見ていても、クマの扱いについてはさまざまな意見があるようです。

2025年、日本各地でクマの出没が相次いだことは記憶に新しい(写真はイメージ。提供:写真AC)
「国民全体での議論もしていかなければなりませんが、まずは現場レベルで問題にどう対応していくかが重要かと思います。
その手がかりとして、Human Dimensionsの理論の中に、『野生動物に対する人間の許容力』というものがあります。これは生態学における『環境収容力』という言葉を意識した概念です。
ある一つの環境、例えば一つの島をイメージしてもらえるとわかりやすいですが、その中で環境を損なうことなく生きていける生物の数には限界があり、この数のことを環境収容力と言います。
それに対して、人間が許容できる野生動物の数にも限界があるんじゃないかという発想が出てきたんです。同じ地域に住んでいるクマの個体数がある一定の数を超え、被害が増えるにつれ、人々はクマの存在を許容できなくなるのでは、ということです。これが仮に0だとしたら、クマは絶滅させるしかなくなってしまいますが、逆にその数字を大きくすることができれば、野生動物との共存の道が開けてくる。そのためにはどうすればいいんだろう?というのがHuman Dimensionsにおける一つのテーマなんです」
まさしく、メディアの報道や普及啓発といった活動が重要になってきそうです!
「メディアのフレーミング効果、つまりどういう切り取り方をするかによって人々の意識に与える影響がものすごく変わると考えられています。テレビのニュースでも、使える時間が決まっているので、『クマが市街地に出没して、被害が出ました』というようなニュースがどうしても多くなってしまいます。それが積もり積もると、見ている人のクマに対する意識がどんどんネガティブになってしまう、つまり許容力が下がってしまうということがあると思います。
一方で、行政による支援や、集落ぐるみの対策をすることで、地域の人々の許容力にポジティブな影響を与えることがわかっています。同じ県内でも地域によって住民の許容力に差があることが意識調査から判明して、何が違うのかを調べてみたら、許容力の高い地域では行政の職員が頻繁に住民とコミュニケーションを取ったり、住民が協力しながら電気柵の設置をしたりしていたことがわかりました。
逆に、そうしたコミュニケーションが希薄な地域では、行政が推奨する対策に対しても住民の理解を得ることが難しく、野生動物に対する住民の意識もネガティブな傾向があったんです」
人間同士の信頼関係が、野生動物に対する意識や対策の有効性にも如実に現れていたということですか。
「私が現在、研究で関わらせてもらっている知床は、世界でもっともヒグマの生息密度が高い地域と言われています。このようにヒグマが多い地域で、住民は長期にわたり、どうやって共存してきたのか、ということを今研究していて、そのキーワードが現地で行われてきた環境教育や普及啓発など、コミュニケーションだと思っています。
地元の小中学校ではヒグマについての授業がカリキュラムに組み込まれていて、子供たちは継続してクマについて学んでいます。それもただ知識として勉強するんじゃなくて、体を動かしながら、実践を通して、ヒグマとどういう距離で出会ったらどういう行動を取るべきか、シミュレーションをしながら勉強しているんです。そういう地域では、子供たちは、もちろんヒグマを怖いと感じることはありますが、知識とスキルがあれば必要以上に恐れることはないと考えていました。つまり、許容力が高い状況にあることが分かったのです。20年近く前から、町の周りを電気柵で囲うようなハード面の対策と、ヒグマ授業というソフト面の対策の両方がなされてきたことが知床の特筆すべき点だと思います」
私も子供の頃に学校で交通事故の授業を毎年受けていましたが、それと同じ感じでヒグマ対策の授業があるんですね。基本的な対策を徹底すればリスクを下げられるという点でも、交通事故みたいだと思いました。
「知床には知床財団という野生動物の専門家の組織があって、財団の職員が地元の学校でヒグマについて教えていたりするので、他の地域でそのまま同じことができるというわけではないです。ただ、交通安全のルールについて誰もが知っていて、全国の子供たちが『赤信号になったら止まる』ことを学んでいるように、クマに出遭ったらどうすべきかも、クマが出没する可能性のある全国の学校で学ぶ必要があるのかもしれません。
大学生を見ていても、そのことを強く感じます。私が所属する政策科学部というところはどちらかというと文系の学部です。『動物が好きで好きで仕方がなくて研究しています』という学生はあまりいません。学生の大半は都会に住んでいて、森を歩いた経験がない学生もいます。そういう学生を連れて毎年知床に行くんですが、やっぱり最初はみんな身構えるんです。それが、実際に現地に行ってみると、街中にヒグマが入ってこられないように電気柵が設置してあって、またヒグマが空けられないゴミ箱の設置など必要な対策がなされていることを学びます。森に入るときはクマスプレイを持ったガイドが同行してくれます。一週間も過ごすと、メディアを通して見る情報は誇張されていて、現地の人は冷静に生きてるんだっていうことに気づいて帰っていくようです」
交通事故のリスクはゼロにはならないけれど、我々はそれを最小化するすべを身につけた上で自動車という便利な道具と共存しています。野生動物との関係もそうなるといいですね。
参考:知床財団が公開しているヒグマ対処法 https://www.shiretoko.or.jp/higumanokoto/bear/

桜井先生のゼミでは例年、知床で実習を行っている
人間と動物の関係、めざす理想とは
桜井先生は、もともと動物が好きでこの分野に進まれたのでしょうか?
「子供のころから野生動物が大好きだったんですが、高校の早い段階で、文系のプログラムを選んだことで、大学は法学部政治学科に進みました。大学の専攻を活かしつつ野生動物と関われないかという思いを抱いて渡米して出会ったのが、Human Dimensionsだったんです。
野生動物の生態は今でも好きで、ここのキャンパス(立命館大学大阪いばらきキャンパス)の中で自動撮影カメラも仕掛けてます。都市部にあるキャンパスでありながら、夜中になるとキツネ、タヌキ、テン、ハクビシン、アナグマなど、あらゆる種類の中型哺乳類が活動してるんです」

桜井先生の職場である立命館大学大阪いばらきキャンパス。街中にあるにも関わらず、夜になるとさまざまな動物がやってくる。写真は自動撮影カメラに写ったキツネ、アナグマ、テン
こんなに都市化されてる地域に、それだけいろいろな動物がいるんですね。
「都市の環境にうまく順応していて、巧みに生きていると思いますね。
もちろん街に動物が出てくると様々な野生動物問題が発生します。でもSDGsとか自然共生社会というスローガンで我々がめざしていたのはそういう世界だったとも思うんです。自然環境と人間社会を切り分けてしまうのではなく、双方が持続可能な形で共生していくということです」
たしかに、そういうものを受け入れられる社会こそが、真に豊かな社会だと思います。
「私が留学していたのはアメリカのフロリダなんですが、あのあたりはものすごくワニが多い地域なんです。大学のキャンパスの中にある大小さまざまな池にも普通にワニがいて、『泳がないで』とか『池の近くで子供を歩かせないで』といった標識が立ってるんです。一見、怖いと言われている野生動物でも、人間の側が注意することできちんと共存ができている。そういうのがフロリダでは実現していて、動物と共存する社会がどのようなものなのか、学ぶことができました」

留学先のフロリダでは、人間とワニとの共存が成立していた
クマの出没は、都市圏に住んでいてももはや他人事ではない。ちゃんとした知識を身に着けて、正しく怖がることが大切だ。それと同時に、野生動物をはじめとした自然をどう受け入れて社会を作っていくか、みんなが考えないといけない時代が来ているといえるかもしれない。
(編集者:谷脇栗太/ライター:岡本晃大)