世の中に溢れる音楽、新しく発表された曲にも「どこか懐かしいフレーズ」と感じ、「これってパクリじゃないの?」と考えたことは少なからずあるのではないだろうか。そんな「パクリ」についての漠然とした疑問を解消すべく、今回は筆者の大学院生時代の指導教官である大阪公立大学の増田聡先生に取材を申し込んだ。先生の専門分野はポピュラー音楽研究やメディア論。数年前、授業で「完全パクリレポート」という課題を出し話題となった。レポートの文章を一字一句、全て既存の文章から「パクって」書かせるのである。そんなユニークな視点から「音楽」「パクリ」を研究している先生にお話を伺った。
2000年代に急激に増加した「パクリ」問題
久しぶりに訪れた研究室で迎えてくれた増田先生。当時は筆者の研究を指導していただき、先生には今も頭が上がらない。面と向かって取材というのは初めてだ。
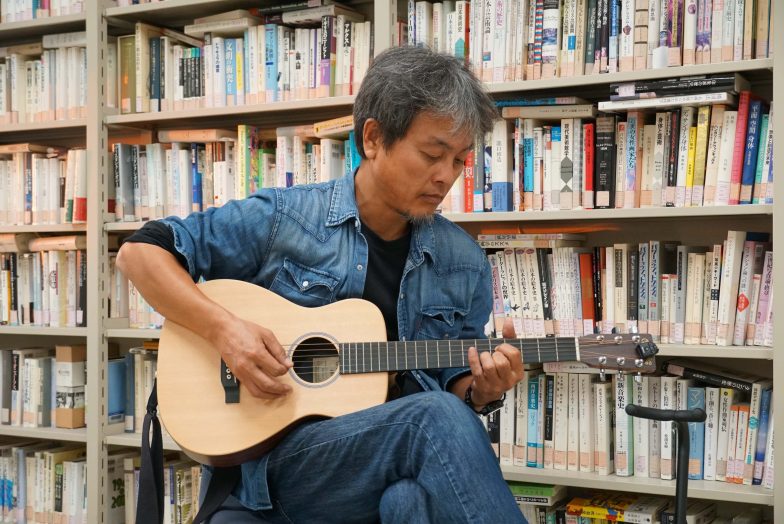
共同研究室にはギターが。はじめにお写真を…とお願いするとさらっと演奏してくださった
——改めて先生の専門分野を教えていただけますか。
「メインはポピュラー音楽研究です。学際的な研究分野でして、音楽学者や社会学者、人類学者、歴史研究者などさまざまな立場の人がいますが、僕は哲学寄りの、美学的な研究を主軸にしています。
ある作品を創作したその人の『オリジナル性』とは何だろう、といったことに関心があり、作者と作品の関係を探究してきました。例えば、ベートーヴェンと『運命』という作品はそもそも別ものなのに、なぜそれがベートーヴェンという人物の何かを表現している、あるいは作品がその作者の内面を反映している、とされるのか。人とその制作作品との関係と、オリジナリティの関係はどのような構造になっているのか、ということに基本的に関心がありました」
——ポピュラー音楽の美学的研究に着目されていたというお話なんですけれども、その観点があったからこそ、パクリという研究につながったんですか?
「そうですね。模倣の問題というのは哲学や美学の中でずっと考えられてきたことではあります。ただ、昔とまったく文脈やメディア環境が違う。20世紀以降のポピュラー音楽の中ではそれをどう位置付けるべきか、を考えています。サンプリングやリミックスといったテクノロジーが存在しなかった時代と今では、模倣の問題は当然変化していますよね。
ネットが普及する80~90年代前半まで、パクリを巡る議論を調査してみますと、よっぽど悪質な剽窃じゃないと表に出てこないんですよね(そもそも盗作や剽窃を「パクリ」と呼ぶのが一般化したのは90年代以降のことです)。なぜかというと、昔は文化の送り手っていうのは、ある程度プロフェッショナルな人々で構成される閉じられた空間・業界にいたんですよ。発信するマスコミ側もいわば同業者のようなものだから、なかなか同業者を倫理的に非難するのは難しいところがあったと思います」
では、ネットが普及してきた2000年代以降はどうなのだろう。先生によれば、朝日新聞の統計データを調べてみると、新聞紙上で音楽だけではなく、小説の盗作なども含めて、パクリにまつわるワードの出現率が爆発的に増えていったらしい。
「いろんな文化リソースへのアクセスということはやりやすくなって、逆に言うと『パクリ』がバレやすくなってきたんですね。典型的なケースを一つ挙げると、80年代にあるロック歌手が、同時代の海外ミュージシャンの曲をほとんど引き写したような『オリジナル曲』を発表したことがありました。当時はパクリだとかそんなことは何も言われなかったですが、2000年代に入って、その曲が入ったアルバムが再発売されるにあたり、付録のブックレットにわざわざ釈明というか反省文のような文章が付けられていた。現在ではその曲はサブスクリプションサービスで聞くことはできなくなっています。要するに、我々が文化の模倣を判断するときに、どれだけ気配りや配慮が必要かということが2000年前後あたりで日本では変容してきたと思われます」

音楽やパクリという切り口から、ネットが社会にもたらしたものの大きさを改めて感じる
「オマージュ」「カバー」「無断使用」「パクリ」という言葉は全部一緒?!
——音楽をはじめ、芸術作品には「オマージュ」や「カバー」といったポジティブな言葉もあると思うんですが、「無断使用」や「パクリ」とはどう違うのでしょうか?
「それらの区別が試みられることは多いのですが、美学的に言うならば根底は一緒です(笑)。すべてをひっくるめて『間テクスト性』という概念で説明することができる。あらゆるテクストっていうのは何らかのかたちで似ていたり、関係を持っている。文化表現は常に間テクスト性の中に置かれているというのが、文化に対する基本的な考え方です」
例えばどんな音楽、文学、映画なども、それのみが独立して存在しているのではなく、先行するあらゆるものと何らかの関係をもっていることを指す概念を、間テクスト性という。
「日本語であれば、どんなものであっても、日本語という基盤によって関連づけられているわけですね。似てるか似てないか、というのはどういう文脈・水準で見るかによって決まってくるわけです。例えば、犬と猿、犬とキジってどっちが似てる?って言われても、人によってその判断はバラバラでしょ?この文学作品とこの作品は文章が一緒とか違うとかいうのも、別の側面から見るならば全部『紙を使っている本』なんだから一緒だとも言える。オマージュは一般的にある先行する優れた作品に対する敬意を込めて、それを一部模倣することを言うわけですけど、経緯とか文脈、時代などが変わるとパクリなどと言われてしまったりもする。さっきの80年代の歌手の例も、発表当時はオマージュとして機能していたはずです」
また、増田先生はX(旧ツイッター)を例に挙げた。いわゆる“クソリプ”はポスト(投稿)の文章をきちんと読んでいない人が多いそうだ。文章の文脈を見ずに前後の流れを無視して、そこだけ揚げ足を取るという。
「ある文脈の中で正当性があった文脈が、全然別の文脈に移し替えられて扱われることが増えているように思います。だから、ある文脈の中で敬意をもったオマージュとみなされたものが、別の文脈では盗作とみなされることが起きやすくなっている」
こんにちの人々は間テクスト性に怯えている、と増田先生は話す。つまり「これはパクリになるかも、誰かに非難されるかも」と逆に萎縮してしまっているという。パクリが増えているというよりは、情報過多の環境が発達したことによって、文脈が切り離され、悪い方向で揚げ足取りされることが一般化した帰結なのではないか―。
「オリジナルな表現がその人に帰属する、という原則だけが何かクローズアップされちゃって、それ以外のさまざまな文化の間テクスト性の扱い方が見失われてる感がありますね」

文化の捉え方への危惧を語る増田先生
最初にふれた「完全パクリレポート」も、間テクスト性について考えさせる意図があったという。このレポートは、自分の言葉ではなく、文献やネットからすべて文章をひろってつなげ、きちんと論を展開する必要がある課題だ。
「あれは元々ヒップホップから着想した課題です。テクノロジーを用いて既存の曲を切り刻みつなげる音楽の作り方はすっかり定着しているんですけど、なぜ文章は1人の著者が選んだ言葉だけで書かれないといけないのか?ということが疑問としてあった。そもそも大昔の文化表現(わらべうたや神話など)に単一の作者はいません。多くの人々が口伝えで伝えるなかでいつの間にかできあがっていった。近代になると、ベートーヴェンのような一貫した主体が一つの作品を形作る、ということが規範となるのですが、現在のテクノロジー環境の中では、音楽を作るにしてもそもそも誰かが作ったアプリケーション上で制作されたりしているわけですよね。一つの文化表現は実は多くの人が『共作者』となっているのが現実で、断片化した創作的な貢献が集まってさまざまな表現が生まれているのが現状です。なのに、我々はついその中に“一人の作者”を見出そうとしてしまう。
そもそも、言葉を考えてみてもそれは自分一人が作り出したものではない(完全に自分オリジナルな言葉は他人に通じません)。他人から与えられたものを選んで組み合わせて『オリジナルなもの』を作るということは、結局、他の楽曲や音源から一部を切り取って再構築し、新たな創造をするという、ヒップホップの基本的な表現方法(サンプリング)とそんなに変わらない。それが社会的な文脈の中で、あるものは『オリジナル』とみなされたり、あるものが『模倣』とみなされたりする。パクリレポート課題はそのような現代のオリジナリティをめぐる状況の中で、意図的・形式的に『パクリ』をやらせてみると教育的な発見があるよね、という発想でやっています」
社会が「パクリ」に影響を与えていた?!
——では、「パクリ」が音楽業界や社会に与えてきた影響とはどのようなものなのでしょうか?
「うーん、これは問いの立て方が逆ですよね。パクリが社会に影響を与えたのではなく、社会がパクリに影響を与えた、といいますか、『パクリ』という世界認識の仕方を社会の側が生み出した、と言えばいいかな。文化表現はそもそも間テクスト性のただ中におかれており、ある表現と他の表現は常になんらかのかたちで関係している、というのが常態です。だから『1個1個の作品がオリジナル』『他のものと関係ない自立的な作品」『個々の作品は全て独自のものであるべき』という見方自体がそもそも文化表現に対する特定の見方を反映しているわけです。しかもこんにちの社会ではそういった見方が、著作権制度のような形で社会構造の中に埋め込まれてしまっている。その結果、他のものと関係していたり似ていたりするのが常態である文化の本来のあり方を、いわば抑圧しているんですよ。
僕に言わせると、今は文化に対する極端な『オリジナル/パクリの二分法』とでもいえる観点が大衆化している。間テクスト性を恣意的にネガティブに捉えたりポジティブに位置付けたりして、同じ実践でも文脈が異なると断罪の対象になってしまったりする。著作権に基づくとこうなるとか、そういった恣意的かつ断定的な現実の制度だけに頼って考えていても文化の現実は把握できません。間テクスト性のような哲学的・原理的な水準から考えていくことが重要だと思いますね」
最後に増田先生は私たちに向けて、支配階級のイデオロギー(政治・道徳・宗教・哲学・芸術などにおける、歴史的、社会的立場に制約された考え方。観念形態)という観点でさまざまな現象を考えれば生きやすくなると話してくれた。
「『これがパクリだ』という断罪や、そもそも『パクリが良くない』という考え方自体も支配階級のイデオロギーなんじゃないか?著作権使って利益を上げている文化産業がわれわれに信じさせたいものの見方に過ぎないんじゃないか?という観点で世の中を見るようにしたら、シンプルに元気になるんじゃないでしょうか。パクリだけに限りませんけど、世の中は複雑で理解不能で、他人と違った変なことをするとネットで炎上するし、訳わかんない構造にこづき回されて生きているって感覚で生きている人は多いと思うんですけど、『支配階級のイデオロギー』を批判する視点を獲得するだけで、生きてるのがつらい人も元気になりますよ。最近は社会的にネガティブなものを研究テーマにするのはおかしいとか、敬遠しようみたいな風潮があったりするんですけど、そういう風潮も(そういう対象にポジティブな側面が見出されたら都合が悪い)支配階級のイデオロギーに侵されているだけに過ぎない。世の中の趨勢に流されず、かといって無視もせずしっかり見据えた上で、芯が通った社会の見方・世界の見方をつくる、考えるのが大切なことです。とくに大学はそれを自分で形作る場だと思いますね」
「パクリ」の話から「支配階級のイデオロギー」につながるとは思わず、とても内容の濃いお話を2時間強聞かせていただいた。「パクリ」というひと言でも、さまざまな事象が絡み合い、意味を成していることがわかった。現実や制度がこうなっているから当然だ、と受け止めてしまう前に、まずそこにある本質とは何か、という問いかけをもつことで、新たな視点が獲得できると感じた。
(編集者:河上由紀子/ライター:小池美里)
