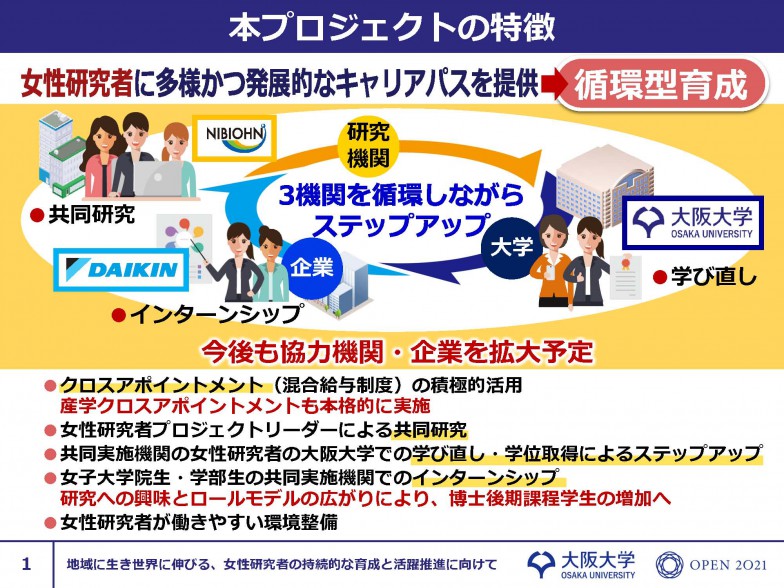人間だけでなく環境の「健康」も担う?食品機能成分を大阪大学で学ぶ。
ワインやチョコレートに含まれるポリフェノール、納豆のネバネバが健康や美容に効果があることはよく知られていますよね。そんな食品の成分をさまざまな領域に役立てる最先端研究を紹介するイベントがあると聞き、大阪大学へ行ってきました。
サイエンスをもっと気軽に、もっと身近に。
参加したのは、大阪大学が市民と大学をつなぐ社学連携、社会貢献の窓口として活動する大阪大学21世紀懐徳堂と、大阪大学歯学部附属病院・大阪大学歯学研究科が共催で定期的に行っている「サイエンスカフェ」です。サイエンスと聞くと難しそうですが、このイベントは「気軽におしゃべり」をコンセプトにミニマムな規模で行われ、先生方が自身の研究をわかりやすく、楽しく解説してくださるもの。
会場も大阪大学歯学部附属病院内の実際のカフェなので、おいしい飲み物とスイーツを特別料金でいただきながらお話を聞くことができ、毎回好評なんだとか。今回も性別や年齢を問わず20名以上の参加者でいっぱいです。

会場の大阪大学歯学部附属病院

入ってすぐのカフェが会場。気軽に参加できる雰囲気
さて、みなさんのお茶とお菓子の準備が整ったところで、イベントがスタート。今回のテーマは「ポリフェノールのイロハ、教えます。〜食品機能成分の最先端研究」。講師は大阪大学大学院工学研究科・宇山 浩教授です。
宇山先生の専門は高分子化学。再生可能な生物由来の有機性資源を原料としたバイオマスプラスチック、微生物によって分解される生分解性プラスチックについて研究しているそうです。
ワインも納豆も。食品の秘めた力を解明、活用。

宇山 浩教授。スライドを使いながらわかりやすく解説
テーマに掲げられたポリフェノールは、宇山先生の研究でも核となる生物由来の有機性資源のひとつで、地球上のほとんどの植物に存在する苦味や色素の成分。緑茶のカテキン、蕎麦のルチン、大豆のイソフラボンなどもポリフェノールの一種だそうです。
「ポリフェノールは紫外線や捕食者からの防衛のために植物自ら産出するもので、抗酸化作用、抗菌・消臭作用、抗アレルギー作用、免疫力向上作用などに優れているのが特徴です」と宇山先生。
医薬品や化粧品、食品といったどのアイテムに、どのポリフェノールを効かせるかは千差万別で、同じお茶でも脂肪の燃焼を促進するポリフェノールを配合したもの、脂肪の吸収を抑制するポリフェノールを配合したものと違いがあるとのこと。ポリフェノールの種類や役割を事前にチェックした上で選べば、より効果を得られるんだなと思いました。
もちろん、宇山先生はポリフェノールをはじめ生物由来の有機性資源の医薬品や化粧 品への活用にも携わっており、その中で、お話があったのが納豆菌です。
納豆は機能性食品として大変優秀。とくにネバネバと糸を引く成分に含まれる「γPGA(ガンマポリグルタミン酸)」は、保湿・保水効果、免疫増強機能などに優れ、抽出・精製すると無味無臭の粉末になるので、汎用性抜群です。
宇山先生はこの特性を生かし、アンチエイジング化粧品の開発をしています。実用化はまだですが、加齢と共に減少する肌内部のヒアルロン酸量を増やし、肌のハリやツヤを保てるとのこと!一刻も早く商品となることを願うばかりです。
「自然に還る・消えるプラスチック」を世界中に!
さて、ポリフェノールや納豆菌の横顔を知ったところで、お話は宇山先生の最先端研究へ。
現在、社会にはさまざまな問題が山積していますが、そのひとつがゴミ問題です。特にプラスチックゴミによる環境汚染は深刻化。石油由来のプラスチックは焼却すると有害物質が発生する場合もあり、かといって自然に消滅、分解することもないですよね。
さらに、宇山先生は海洋汚染も懸念しています。「海は地球に1つで、世界とつながっていますから、ある国で捨てたプラスチックゴミが違う国に漂着したり、数十年から数百年も漂流し続けたりします」。

今まさに取り組んでいる研究ということで、お話にも熱が入る
しかも、この漂流によって劣化、微細なマイクロプラスチックとなることも問題。餌と一緒に捕食した魚の体内に残留、それを将来的には人間が口にすることになる可能性もあるからです。お刺身やお寿司が好物の筆者は死活問題…。
そこで期待されるのが、宇山先生が研究している、ポリフェノールをはじめ生物由来の有機性資源を原料としたバイオマスプラスチックや生分解性プラスチックです。
例えば、生分解性プラスチックは水と二酸化炭素に分解されるので、環境への負担がなく、ゴミ問題の解決にもつながります。「ただ、世界のプラスチック生産量は年間4億トン、うち生分解性プラスチックは91.2万トンと、全体のたった0.2%程度(2018年)。製造・販売のコストダウン、分解速度のスピードアップといった課題もあります」。
しかし先生は「普及にはまだ時間を要しますが、人類や地球の未来のために研究を進めています」との言葉でサイエンスカフェをしめくくりました。

先生のコメントが掲載された記事も配布された
身近な食品の効果活用から人類や地球を救う構想まで。理系が大の苦手な筆者も宇山先生の研究の幅広さと奥深さに触れることができ、有意義な時間を過ごすことができました。また、自らが口にする食品、健康、そしてゴミの減量など、見直すべきことがたくさんあることも実感。学びと共に、気づきの機会も与えてくれる大阪大学「サイエンスカフェ」にみなさんも参加してみてください。
取材協力:大阪大学21世紀懐徳堂