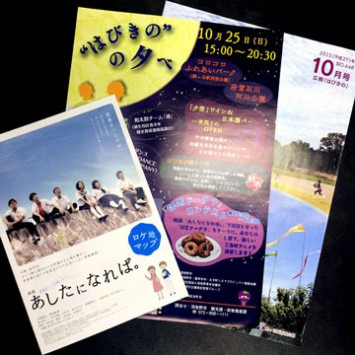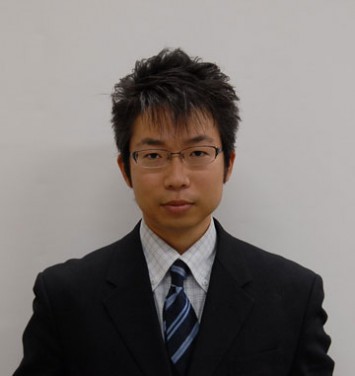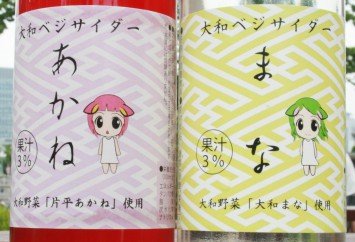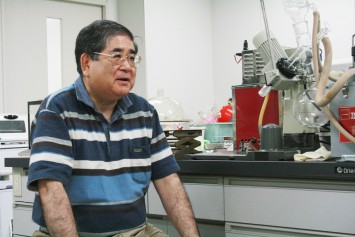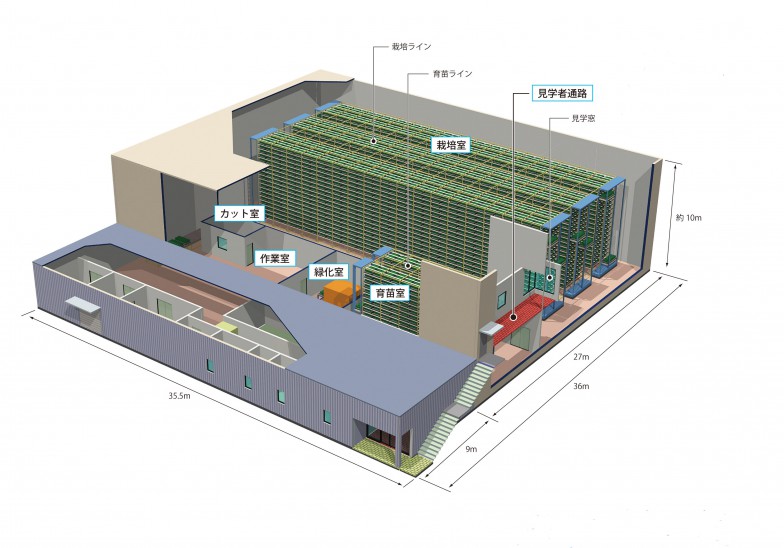府立大発スイーツ第3弾「いちじくほっぺ」ができるまで(後編)
2015年11月25日 / 大学発商品を追え!, 大学の知をのぞく
学生がいちじくのスイーツを企画・開発する意味
ただ今『ほとゼロ』にて追いかけている、「Habikinoいちじくプロジェクト」第3弾、「いちじくほっぺ」発売までの道。前回のレポートでは羽曳野市役所訪問までをお伝えしたが、今回はその後、大阪府立大学羽曳野キャンパスを訪問した模様をレポートする。
(参照:府立大発スイーツ第3弾「いちじくほっぺ」ができるまで(前編))
この日は、「いちじくほっぺ」の製造元となるみどり製菓が商品化に向けて作った、試作品の試食会の日。案内された実習室に入ると、そこには黒川通典講師と、みどり製菓の翠紀雄社長、製造担当の井﨑宏治さん、そして大量の試作品がスタンバイしていた。そこへほどなくして、「いちじくほっぺ」の生みの親である学生たちが到着。彼女たちはすぐに試作品の山へと駆け寄り、「かわいい!」「すごい!」とワイワイ、キャーキャー、大興奮。スマホで写真を撮りまくってはしゃいでいる。正に、今時の学生そのものだ。

試作品を前にはしゃぐ学生のみなさん

「いちじくほっぺ」の試作品
しばらく落ち着きそうにないため、まずは学生たちを温かな目で見守る黒川講師に、改めてこのプロジェクトを始めたワケを直撃してみる。

プロジェクトをまとめる大阪府立大学 大学院 総合リハビリテーション学研究科 黒川通典講師
「『Habikinoいちじくプロジェクト』は3年前、みどり製菓さんから『羽曳野のいちじくを使った大阪ならではのスイーツを作りたい』とご相談いただいたことをきっかけにスタートしました。いちじくは地元羽曳野の特産品であるのですが、傷みやすく、あまり流通には向いていません。また、売れ残ったものは廃棄されることも知りました。大学としては地元のこうした課題に向き合わないといけないと思いました。生のいちじくは傷みやすくても、スイーツに加工すれば流通するんではないかと。ちょうど学生たちには経営管理を教えていたので、テーマとしてもおもしろいことから、授業の数コマを使って『売れるいちじくスイーツの企画・開発』を始めたんです。最初はターゲッティングから始めましたが、意外にも学生たちの多くはいちじくって何? という反応でした。最近の若者はいちじくを知らないんですね、驚きました。そこでまずはいちじくのことを知ってもらおうと商品企画のターゲットは学生たちのような若い女性に決まりました。」
確かにいちじくは、数あるフルーツの中でも、わりと地味でマイナーなイメージ。若者が好きなスイーツと言えば、マンゴーとかイチゴとか? いちじくと同じ秋のスイーツなら、ぶどうや梨、柿あたりだろう。
こうして『Habikinoいちじくプロジェクト』は実施されることになったのだ。学生たちは休みの日を使って道の駅でのリサーチを行なったり、すでに販売されているいちじくのお菓子の調査を行い、あるいはいちじく農家を訪れるなど、ただ自分たちが“食べたいもの”ではなく、マーケティングもしっかり行った上で、“売れるもの”としてのいちじくスイーツ開発に奮闘している。
容赦ないダメダシの嵐
さて、先程まで試作品を前に熱狂していた学生たちだが、いざ試食を始めると、彼女たちの口からは次々に意外な言葉が飛び出してきた。
「モチモチ感はあるけど、フワフワ感がない」
「コーティングのチョコが分厚いから、生地よりチョコの方に気を取られる」
「見た目の色が、思っていたのと全然違う」
等々。さっきまであんなに喜んでいた(ように見えた)のに、厳しい評価がくだされる。翠社長と井﨑さんに対してけっこうズバズバ言うので、見ているこっちは内心ヒヤヒヤ。だが、それだけ学生たちも真剣に取り組んでいるということの表れなのだろう。
そんな彼女たちに話を聞くと、「いちじくほっぺ」のポイントは、まず食感にあるという。
「普通焼きドーナツは重いものが多い中で、私たちは子どもから大人までおやつとして手軽に食べられるよう、軽めの食感をめざしたんです。それに、テーマである初恋を経験する年代って中学生ぐらいかなということで、まだあどけなさの残る中学生の柔らかなほっぺたをイメージして、モチモチ・フワフワ食感を追求しました」
試行錯誤の末、タピオカ粉と豆乳でモチモチ感を、シフォン生地でフワフワ感を出すと決めてからも、配合が難しく、何度となく調整して大変な思いをしたそうだ。2ヶ月という短い準備期間の中、ドーナツが嫌いになるぐらい、試作と試食を繰り返した。
このレシピに対してみどり製菓側は、
「商品として流通させるためには日持ちすることが大切なのですが、学生さんたちのアイデアそのままでは、時間が経つと生地がパサパサになったり縮んだりしてしまいます。そこで、生地の食感を保ちつつ2ヶ月は日持ちさせるために、チョコレートでコーティングしました。チョコレートにはドライいちじくの粉末を混ぜて、いちじくらしいプチプチとした食感も出しているのですが……」
結果、分厚いチョコレートが優勢となり、学生たちこだわりのフワフワ感がやや落ちてしまったようだ。

厳しい目で試食する学生たち。みどり製菓の翠社長、製造ご担当の井崎さんと真剣な意見交換がなされる。
また、「いちじくほっぺ」のもう一つのポイントは、学生たちが掲げた商品コンセプト、“クール×恋心”に基づくデザイン。
「表面的にはクールな表情を装っているけれど、それは照れ隠しで、心には熱い思いが秘められている。そんな初恋のイメージで、表面に白いアイシングを施し、中に白ワインジャムを入れました。生地にはいちじくジャムを練り込んでいます」
一方、みどり製菓による試作品の見た目は、鮮やかなピンク色である。食紅で染めたチョコレートでコーティングされているためで、これには学生から、
「見た目は白くしてほしいし、材料に食紅を使うのもやめてほしい」
とオーダーが出されていた。みどり製菓側は、
「初めはもう少し薄いピンク色だったのに、時間が経つとこんな色になってしまって……」
と前置きしつつ、
「とにかくキツイ色はやめて、白のイメージに近づけます。例えば、食紅ではなくいちじくジャムを使ってほんのり赤く染めるなど、淡い初恋の雰囲気が出せるように改良してみますね」
と応える。学生の想いを尊重しつつ、商品化にあたっての条件をクリアして、さらにより魅力的に仕上げる。そんなプロの仕事を垣間見た気がした。
「いちじくほっぺ」の改良はまだまだ続く
実は、この試食会には「いちじくほっぺ」以外に、もう2種類別の試作品が用意されていた。それは、6チームによるプレゼンテーションでは惜しくも優秀作品には選ばれなかったものの、その完成度の高さから商品化が検討されているという、別チームが考案したフィナンシェ風ドーナツ。こちらについても「いちじくほっぺ」同様、担当学生たちとみどり製菓側による熱いやり取りが繰り広げられていたのが印象的だった。遅かれ早かれ、商品化は間違いなさそうだ。

フィナンシェ風ドーナツの試作品。
こうした学生たちとのコラボについて、翠社長と井﨑さんに率直な感想を伺うと、
「学生さんたちは、アイデアも発想もとにかく自由。全然偏っていなくて、いろんな世界を見ていて、こちらが思いつかないような提案がたくさんあって、驚かされるばかりです。それに、プロ顔負けの技術を持って試作品を作り、プレゼンテーションされるので、本当に感心しますね。そして今日は改めて、商品化に向けては、もっと学生さんたちが考えられたコンセプトを大事にしないといけないなと、思い知らされました」
と話してくれた。

製造に携わるみどり製菓株式会社の翠紀雄社長(左)と同社製造担当の井崎宏治さん(右)
今後、さらなる試作を進めつつ、パッケージデザインや販売価格についても学生たちと検討していくと言う。いったいどんな形に仕上がるのか。続報を楽しみにお待ちいただきたい。