もしも不死の生命を手に入れることができたら、人間は幸せになれるだろうか?
あるいは、優秀な人工知能がすべてを決めてくれる社会は「良い社会」だろうか?
これらの問いは、小説や漫画、映画といったフィクションの世界でしばしば描かれてきたものだ。少し前なら絵空事と笑ってすませることができたかもしれないが、現実に起きているAIの急速な進歩と浸透を目の当たりにしていると、どうにも笑っていられなくなる。
並行世界や遠い未来などなど、現実とは少しズレた世界を描いた物語の中にこそ、現実の諸問題を考えるヒントがある――そう話すのは、10年近くにわたってSF漫画を題材に哲学や倫理学の講義を行い、昨年『SFマンガで倫理学 何が善くて何が悪いのか』を上梓した広島工業大学の萬屋博喜先生だ。荒唐無稽な設定の漫画から、一体どんな問いを読み取ることができるのだろうか? お話を伺った。
人としてのルールを批判的に検証し、「善いこと・悪いこと」を突き詰める
英語圏の哲学が専門で、特に最近は「行為の哲学」を研究している萬屋先生。たとえば、落雷でパソコンが壊れてしまったとして、自然現象に責任を問うことはできない。しかし、だれかが意図的にパソコンを床に落としたときなど、人間の行為には責任を問うことができる場合がある。行為とはなにかを分析することが、倫理学を研究するうえでの重要な前提になるそうだ。
ところでそもそも倫理学って? 学校で習う道徳や倫理とはどう違うのだろうか。
「倫理学とは文字通り、倫理についての哲学です。倫理や道徳は、人間が集団生活を送るなかで、人として従うべきルール(モラル)のことといえるでしょう。自然に出来上がってくる倫理と制度化された道徳は別物だとする考え方もありますが、大きな意味では同じものだと私は考えています。ただし、そうしたルールの学び方には2つのアプローチがあるんです。それが道徳教育と倫理学です。
みなさん、小学校で道徳という科目を習いましたよね。道徳教育は、人に優しくしなさいとか、嘘をついてはいけませんとか、いわば先人が示した人としてのルールを習得して、実践できるようにするためのものです。
対して、それら既存のルールを批判的に検証して、『何が善いことで何が悪いことなのか』という議論の前提になるような出発点まで立ち戻って考えるのが、倫理学なのです」

Zoomでお話を聞かせてくださった萬屋博喜先生
道徳、マナー、法律や規則など、世の中には明文化されている・いないにかかわらずさまざまなルールがある。ルールを守っていれば日常生活で困ることはなさそうにも思えるけど、倫理学を学ぶ意味はどんなところにあるのだろう。
「たとえば現在、生成AIをめぐっていろいろな議論が交わされていますよね。誰もが簡単に生成AIを使えるようになってはじめて、著作権侵害などの問題が認識され、法整備の必要性が問われはじめています。法律や道徳教育は、どうしても現実の後追いになってしまう。一方、倫理学は、『仮にこういうことが起こった場合にどう考えるべきか』という仮定のもとで議論を積み重ねていくことで、将来起こりうることについても事前に考えて備えることができる。私たちが進むべき道について先読みできるんです。
それに、世の中で正しいとされているルールでも、別の側面から見たときに間違っていることもある。そうした既存のルールの点検作業をすることで、人々が間違ったルールに苦しめられることを防ぐのも倫理学の役目です」
未来について考えたり、世の中を違う側面から見たり……たしかに、倫理学にはSF的な想像力に通じるところがありそうだ。
『火の鳥』『寄生獣』から感じたモヤモヤに、倫理学が手がかりをくれた
萬屋先生が青春時代を過ごした1990年代後半は、阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件、酒鬼薔薇聖斗事件と、世の中の倫理観を揺るがす出来事が相次いだ時期だ。宗教が抱える問題、「キレる17歳」と世代で括られることの暴力など、萬屋少年の中で後に倫理学への興味につながる問題意識がふつふつと育っていた。それと同時期に出会ったのが、いくつかの漫画だったそうだ。
「当時、図書館に置いてある漫画といえば『はだしのゲン』か『火の鳥』ぐらいだったんですよね。原爆被害の凄惨さを描いた『はだしのゲン』を読んで衝撃を受けたんですが、『火の鳥』はそのときほとんど理解できなくて。でもわからないなりに、何かモヤモヤが残ったんです。それから、友達から借りた『寄生獣』も読みました。周囲の友達はストーリー展開やキャラクターの話で盛り上がっていたんですが、自分が引っかかってるのはそこじゃないんだよなとまたモヤモヤして……。後になって倫理学と出会ったとき、そのときのモヤモヤの正体が倫理学の問いだったんだと気がついたんです」
手塚治虫の『火の鳥』は、不死をもたらす火の鳥を巡って運命に翻弄される人間たちを描いた傑作だ。冒頭に挙げた「不死は人間に何をもたらすのか」といったテーマのほか、クローン人間やロボットなどさまざまなキャラクターを通して、人間が生命を操作することの是非を問いかけてくる。萬屋少年をモヤモヤさせた「なぜクローン人間を造ることは『悪い』ことなのか」……という問題も、まさに生命倫理に関わる問いだ。
岩明均の『寄生獣』は、人間に寄生する宇宙生物パラサイトと主人公の奇妙な共生関係を中心に、それをとりまくキャラクターたちが織りなす群像劇。作中でパラサイトの側に立つある人物は、「人間こそが地球に寄生し蝕む存在なのではないか?」と問いかけ、善悪の価値観に揺さぶりをかける。倫理学では人間中心主義/人間非中心主義の対立として議論されてきた問題である。
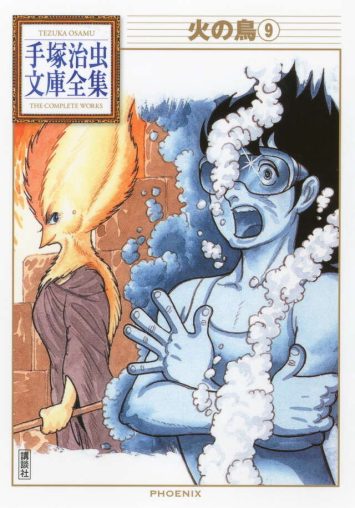
手塚治虫文庫全集『火の鳥⑨』 (講談社)©手塚プロダクション
人間のクローンをテーマにした「生命編」が収録されている
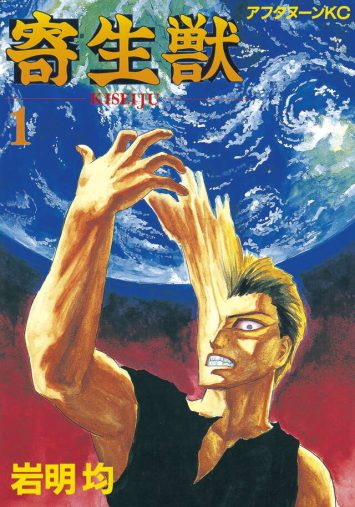
岩明均『寄生獣』1巻(講談社)
「今でこそ大人も漫画を読んであれこれ考察するのがブームになっていますが、当時は漫画=娯楽という偏見が残っていたので、周りにいくらその深さを説明しようとしても理解してもらえないことが多かったですね。私自身もそれを伝える道具立てを持っていませんでしたし……。
大学で講義を持つようになったときに教材として漫画を選んだのは、ページやコマ単位で議論の題材を提示しやすかったからという側面もあるんですが、思考の媒体としての漫画の力をアピールしたいという気持ちもすごくありました。倫理学のメガネをかけて漫画を読むこと、それ自体が倫理学的に思考していることになるんだ、と。自分で振り返ってみても、かなり大胆なことをやってきたなと思います(笑)」
SF漫画『地球へ…』から、AIが普及する現在への警告?
思考媒体としての漫画の力、とりわけSF漫画の力とはどんなものなのだろうか。
「SFで描かれるのは、現実とは少し違う並行世界や、現実の延長線上に訪れるかもしれない高度な科学技術社会、文明崩壊後の未来など、私たちの現実からズレた世界です。世界の前提が変わっても、人間の価値というものは変わらずあり続けられるのか? それが絵と言葉のセットで提示されることで、その世界の生活に入り込んで考えやすくなる。漫画を通してズレた世界について考えることが、ひいては私たちの現実について考えることにもなってくるかもしれません」
例として萬屋先生が挙げたのが、竹宮惠子の『地球(テラ)へ…』だ。舞台は遠い未来。人工知能によって統治された社会で、超能力に目覚め人工知能の支配から脱却した新人類ミュウと、人工知能から新人類抹殺を命じられた旧人類、双方の視点で物語は描かれる。迫害から逃れて宇宙を流浪するミュウたちは自らの意思で考えて行動するが、旧人類は人工知能の「助言」を決して疑わない。物語の後半、地球に降り立ったミュウは旧人類に対して人権を求め、「人の心が決定した結果になら従おう」と語りかけるが……。
「『地球へ…』で描かれるのは、コンピュータにすべての判断を委ねた人類社会です。この漫画が連載されていたのは1977年~80年ですが、半世紀近く経った今、生成AIの普及でまさにそんな時代が訪れつつあるのではないかと思っています。AIに尋ねれば、人間が頭を寄せ合って議論するよりも遥かに早く、合理的な答えを提示してくれる。政策立案や政治的な意思決定にAIが導入されるのも時間の問題ではないでしょうか。
倫理学者のなかには、『人工知能が〈道徳的助言者〉として設計されれば、人間の良き相談相手になる』とする意見もあります。それに対して、『はじめは良き相談相手であっても、いつの間にか人工知能に判断そのものを委ねてしまうことになるのだ』という指摘もあります。まさに『地球へ…』で描かれた未来ですね。
もう少し日常に近づけて考えてみると、たとえば大学の授業で出された課題に対して、AIが出したいくつかの選択肢から人間が最良と思うものを選ぶことは、その人の回答として認められるでしょうか。学生が提出した課題を採点する教員としても直面せざるを得ない問題です。あるいは、SNSを見ていてもAIを思わせるアカウントが会話しているのをよく目にします。人間の意見とAIの意見を区別することは、すでに想像以上に難しくなっているかもしれません」
AIはものすごく便利で、医療から芸術まであらゆる分野に貢献しているのは紛れもない事実だ。けれど『地球へ…』に学ぶならば、人間が自分の頭で考えることを手放してはならない一線というのもきっとあるような気がする。はたして私たちは、AIとうまく共存していくことができるだろうか。
多視点から漫画の世界に入り込み、「自分の答え」を見つけてみよう
昨今流行りの「〇〇について考察してみた」系動画は、作品の中に隠された「正解」にいち早くたどり着こうとするゲームのように見える。「そういう答え合わせ的なものが流行るのは少し怖いですね」と萬屋先生。著書や講義では、作品の中に描かれたテーマに対して倫理学の観点から複数の考え方を提示しつつも、最後は必ず「あなたはどう思いますか?」と投げかける形にしているという。
「ものごとに自分なりの答えを見つけることと、絶対の答えを求めることを混同してほしくないんです。倫理学にとって大切なのは、外から与えられた答えに頼らないことです。主張には自分の生き方や経験が反映されていないといけない。だから白黒つけられない問題が多いですし、ずっと議論が続いている。
誤解してほしくないんですが、だからといって答えがないわけじゃありません。『私はこういう根拠があって、この答えにたどり着いた』ということが言えれば、それは立派な『あなたの答え』として、倫理学の議論で価値を持つことになるんです」
漫画を読むときも、私たちは主人公の感情や主張だけを絶対的な答えとして受け取っているわけではないと萬屋先生は言う。たしかに、吾峠呼世晴の『鬼滅の刃』について言えば、主人公である炭治郎の常軌を逸した純粋さには到底ついていけないし、人間くさい事情を抱えた鬼の側に共感することもある。もう少し俯瞰すれば、ト書きで挿入されるような作中の社会の仕組みにも思うところがある。作者が描きたい大きなテーマは一貫していたとしても、「そのテーマを受け取って、あなたならどう思うか」と問えば十人十色の答えが返ってくるだろう。
そうやって見つけた自分なりの答えやモヤモヤを、倫理学の問いとして深めていくには、どうすればいいのだろうか。
「先ほど、倫理学のメガネを掛けて漫画を読むことが思考することになる、と話しました。そのメガネとは、これまで倫理学で扱われてきたトピックや理論に関する知識です。前提知識をもったうえで作品を読めば、あなたの中でモヤモヤしていたものがクリアに見えてくるはずです。『SFマンガで倫理学』でも、扱うトピックごとに哲学者や倫理学者の理論を紹介していますし、それでもっと知りたいと思ったら個別のテーマや理論に関する入門書を読んでみることをおすすめします。知識を身につけて、フィクションの中で思考して、現実の生活に当てはめてみる。これらを行ったり来たりすることが、世の中のルールや善悪について考える訓練になるでしょう」
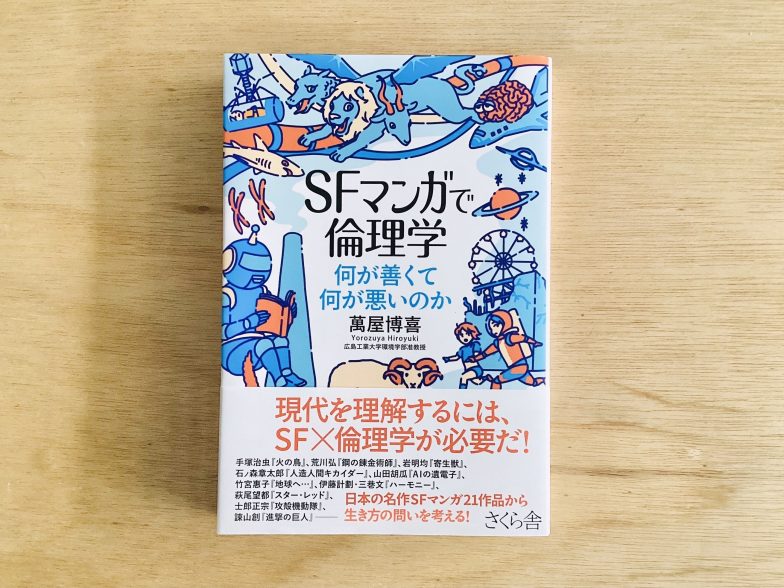
萬屋博喜先生の著書『SFマンガで倫理学』(さくら舎)
「このマンガがすごい!」に選ばれた最新作から往年の名作までくまなくチェックして、倫理学のトピックに合うものを探しながら講義を組み立てているという萬屋先生。倫理学ではまだ開拓されていないテーマが漫画の中から見つかることもあるというから、フィクションの力は底知れない。
「現実に社会で起こっている問題について、すぐには答えの出ない議論をするのはなかなかしんどいものです。そのため、現実社会の複雑な問題を直接考えるのではなく、フィクションというフィルターを通して考えれば、ディスカッションにおいても心理的な安全を確保しつつ、遠慮なく意見を交わすことができる。それもフィクションの力です。一方で、受け取り方を誤れば、作中に描かれたことが真実なのだと思い込まされてしまう恐ろしさもあります。どんな作品も多様に読むことができるはずですから、教材にする際も何か絶対的な答えを導くような扱い方にならないように注意したいですね」
現実世界では、AIだけでなく戦争、差別、環境問題と大嵐が吹き荒れている。これまで正義だと言われていたことが簡単にひっくり返される日々に、心が慣れてきてしまってはいないだろうか。けれど人として生きていくなら、譲ってはいけない倫理の一線がどこかにあるはずだ。荒野で迷子にならないように、SF漫画で自分の答えを見つける訓練をしてみるといいかもしれない。
