大阪大学では、研究者・専門家が地域の人々とさまざまなトピックについて考えるイベント「阪大ワニカフェ」を定期的に開催しています。2025年1月に大阪の千里文化センター「コラボ」で催された第24回では、元大阪大学大学院文学研究科、臨床哲学分野の教授で、現在は一般社団法人 哲学相談おんころの代表理事を務める中岡成文さんが登壇。臨床哲学の歴史の説明やクイズ、大学院生の研究発表など、参加者との対話で臨床哲学の魅力を探るひとときとなりました。
クイズ形式で学ぶ、臨床哲学のあり方
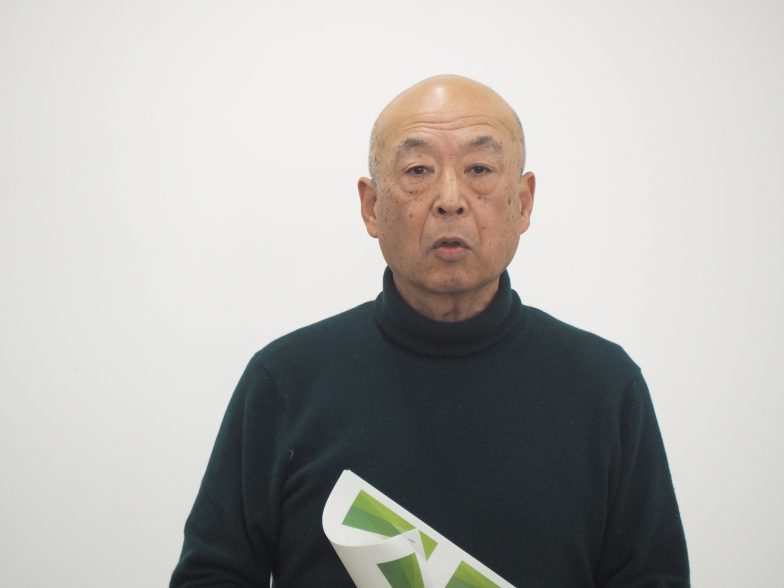
講師の中岡成文さん。がんや難病(ALSなど)の当事者との哲学対話を行う「おんころカフェ」の企画運営をはじめ、哲学対話の普及に取り組む
哲学のなかでも今回のテーマである臨床哲学とはどのようなものなのでしょうか。中岡さんは、まず自身が考える哲学について「哲学は、他の学問と比べて明確な形がない。哲学をするという行為があるだけ」と話しました。社会学や人類学にも大きな関心を持っているといい、哲学との接し方については、哲学者・ヘーゲルの唱えた方法論にもとづいて「前提がゼロの状態から始め、もともとの言葉が持っている意味を壊し、捻ることが大事」と語りました。
臨床哲学という言葉は、中岡さんが着任した大阪大学文学研究科の研究室から始まったといいます。同研究室で同僚だった哲学者・鷲田清一氏が、臨床教育学などからヒントを得たことで提唱されるようになりました。臨床教育学とは、教育現場で子どもたちをあらゆる面からサポートするため、従来の学問の枠を越えた多様な側面から解決を試みるための学問とされています。
臨床哲学は、社会における課題が生じる現場に寄り添い、苦しみや戸惑い、驚き、憤りといった感情も含めて考える哲学的な営みとされているそうです。敷居が高いイメージのある哲学を人々の営みの場に戻すことを目的としているといいますが、中岡さんは、今回のイベントでは、あえてその目的を意識せず、自分の考える臨床哲学と、参加者が考える臨床哲学がどのようなものなのかをディスカッションしたいと訴えました。

前半では臨床哲学に関するクイズを実施
そこで行われたのは臨床哲学に関するクイズです。「ソクラティク・ダイアローグ(※一つの課題に対して丁寧かつ濃密に対話を行う、哲学教育の方法に由来するワークショップ)は、古代ギリシャの哲学者・ソクラテスにならい、知的権威によって、市民に哲学を教える(ものである)?」など、興味深い質問が投げかけられ、参加者は挙手によってイエス、またはノーの回答を行いました。
ちなみに、ソクラティク・ダイアローグの答えは「権威ではなく具体的事例にもとづいて対話を促し、市民が自分で哲学するようにさせる」ものであるとして、答えは「ノー」。その他の質問のいくつかは中岡さんの実体験をもとにしており、臨床哲学の草創期のエピソードからは、「ケアの本質とは何かを議論した際、それは『傷つけるケア』だと主張した大学院生がいる。その大学院生の(現在の)職業は?」と出題し、A.看護師、B.コメディアンという2択が提示されました。(正解はAの看護師)
その大学院生というのは、精神科病棟に看護師として勤務しながら臨床哲学の活動を行った西川勝氏のこと。『ためらいの看護 —臨床日誌から—』(岩波書店、2007年)という著書もあることが紹介されました。
傷つけるケアとは、当然ながら物理的な意味ではなく、対話する相手の心の弱さや傷つきやすさを聞き出すことで、相手(の内面)を傷つけることがケアになることもある、という考え方をいうそうです。中岡さんは臨床哲学を語るうえで重要な考え方だと話しました。

クイズの背景とともに臨床哲学のあり方を解説
クイズのあとの質疑応答やディスカッションでは、ケアや介護が話題に。「介護の対象が、もしロボットや精密機械であっても、人間は適切に介護ができるか」というテーマで議論が白熱。これは、臨床哲学の草創期に、ある大学院生が発した「現代の看護は相手に左右されずに遂行できる完成されたシステムである」という投げかけから導き出されたテーマだそうで、臨床哲学が科学技術や人間との関係性など、現代社会と密接にリンクした分野であることを感じさせました。
学生2名の研究から見えてくる、臨床哲学と日々の暮らしの関連性
後半では、臨床哲学を研究する大阪大学の大学院生2名が、それぞれ「東日本大震災で被災した福島・浜通り地域での哲学的取り組み」「時間の多様性」というテーマで研究発表を行い、それを基にした対話が行われました。
大阪大学大学院人文学研究科2年生の廣畑さんは、大阪大学の核物理研究センターが取り組んでいる福島県原発事故を巡る問題を考える研修会に運営スタッフとして参加し、現地での実習を含む研修会における、「参加者同士のグループワークの中で哲学対話的な場をつくる」という取り組みをされているそうです。

福島県での取り組みについて語る廣畑さん
原発事故を中心に、浜通り地域(福島県東部の太平洋沿岸地域)で起きている産業の衰退、復興に対する心理的不安という問題に、県外の人間がどのように向き合うかを考え続けてきました。その結果として、現地の人々から発せられる言葉を哲学の理論に当てはめず、対話や問題の内容を丁寧に見続け、明確な答えがない中でもネガティブ・ケイパビリティ※を実践することが「私が、研修会のような組織が向き合うべきだと考える取り組み」であると語りました。
※不確実なものや解決していない事柄を受け入れる力のこと。19世紀イギリスの詩人、ジョン・キーツが提唱し、医療や看護、心理学の分野で注目されている
発表が終わると参加者から「問題解決のための対話や哲学カフェなどに参加しない、積極的ではない人も取りこぼさないためには、どのような取り組みが必要か」という質問が投げかけられました。廣畑さんは、「なかなか対話の席につかない人に対しては、辛抱強くコミュニケーションを取る、そのうえで方法論を振りかざすのではなく、腹を割って話し合うのが最善の方法」と経験に基づく見解を語っていました。
ここで、中岡さんが客席にいた大阪大学大学院人文学研究科の准教授・西村高宏先生を紹介し、コメントを求めました。西村先生は東日本大震災で被災し、その後、被災者との対話を行う哲学カフェを現地で主催しているそうです。その経験から、廣畑さんの取り組みに対して、「廣畑さんは、いろいろなことにつまずきながらも現場の人たちの意見を聞き、思考を巡らせる忍耐力を持った人であることが伝わってきました。震災の状況下において哲学カフェは、『あそこに行けばいろいろな話ができる』という希望の場であることが大事です」と意見を語りました。これを受けて廣畑さんは、研修会では、現地の人たちとの対話の場を作ることに対し教員側の理解を得ることが難しかったこと、同じ志を持つ仲間がいたからこそ活動を続けられたことなど、当時の状況を語っていました。

後日開催された阪大ワニカフェにも登壇した西村先生
大阪大学大学院人文学研究科1年生の船橋さんは、大阪大学とは別の大学を卒業し、一般企業に就職しました。しかし、目まぐるしい日々の中で自分を見失い、自分にとっての幸せや、よく生きることの意味を考えるようになり、臨床哲学の道に足を踏み入れました。最初は研究の方向性に悩んだ船橋さんでしたが、人間が感じる時間のスピード感やリズムが一人ひとり違っていることに着目し、テーマを「時間の多様性」に設定。現在は、働き方改革やライフスタイルの多様化によって注目されるようになった時間と生活の関連性や、多忙な日々の中でも豊かに暮らす方法について研究を続けています。

研究テーマである「時間の多様性」について語った船橋さん
具体的にどのような形で時間と向き合っているのかという質問に、船橋さんは「一般的には、議論など知的な作業をする時間の優先度は高いといわれていますが、私は、ご飯を作るなど、日常的な時間も同じぐらい重要であると意識して、自分の時間を豊かにしたいと考えています」と話しました。研究の主軸として、ドイツの文学作家であるミヒャエル・エンデの提唱する時間の豊かさを参考にしていること、また、現在の日本人の時間の使い方が近代に西洋から持ち込まれたものであり、それ以前の人々の生活との違いについても研究を深めたいと語りました。

イベントでは臨床哲学に関するさまざまな意見交換が行われた
イベントは、約2時間という長時間にもかかわらず参加者が常に登壇者の発表に耳を傾け、積極的に発言するなど、終始熱気をはらんだまま終了しました。
かつて中岡さんは、「哲学に関して話し合うようなイベントが、はたして成立するのだろうか」「哲学そのものの意義ではなく、教授という権威性に注目されて人が集まる状況は適切ではないのでは」という疑問に対して大いに悩んだとのこと。それでも、難病の患者や、その家族を対象とした哲学対話の進行やグループセラピーを通して、自由に意見を交わす重要性を感じ、臨床哲学の意義を見出したといいます。
難解なイメ―ジを持たれがちな哲学を身近なものとして考えさせる臨床哲学は、今後、社会課題と向き合う上で存在感を増すのではないでしょうか。
町の人々が、ふと疑問に感じたことを解決するために臨床哲学という考え方を知る、そのきっかけとして阪大ワニカフェのようなイベントがさらに広く浸透することを期待したいと思います。
(編集者:河上由紀子/ライター:伊東孝晃)
