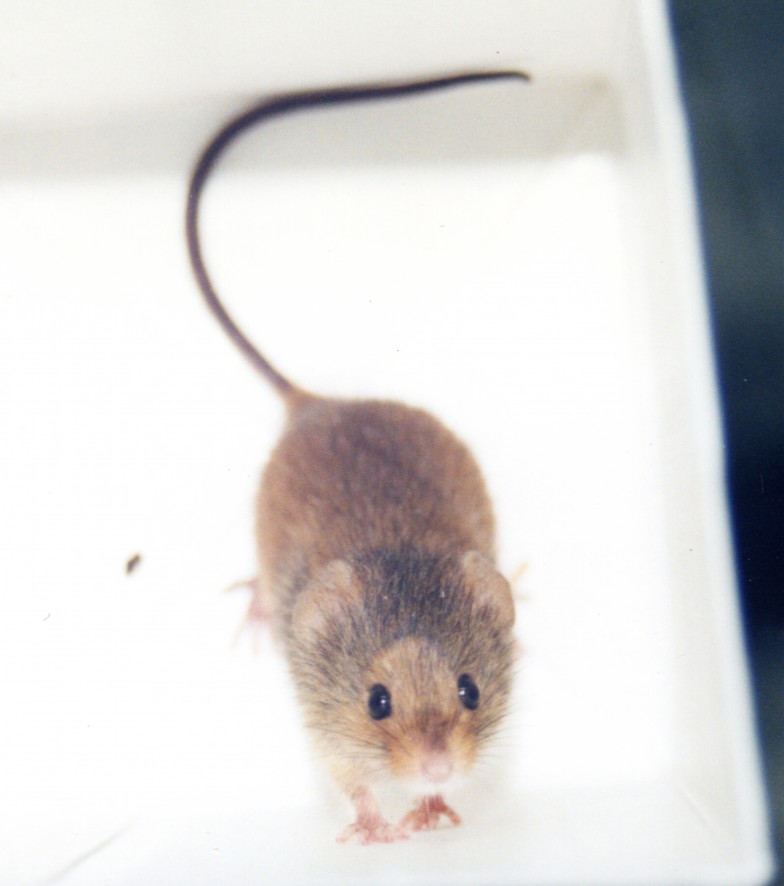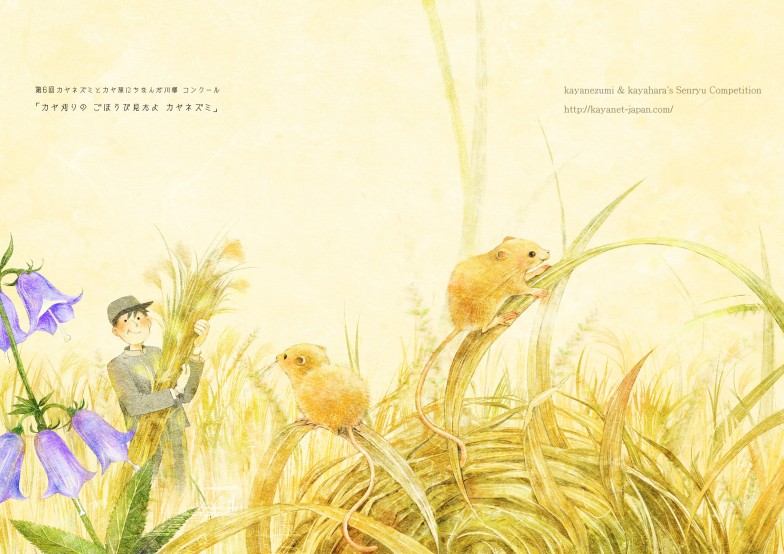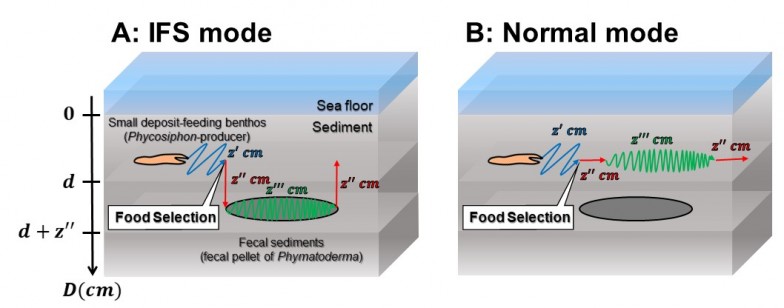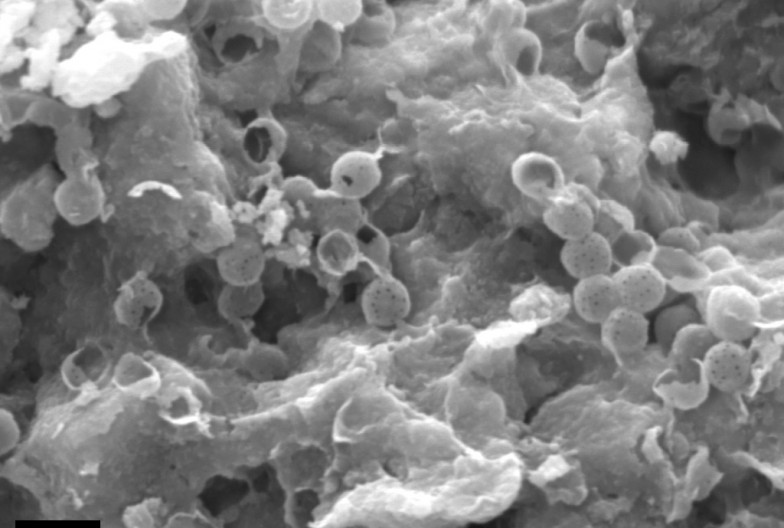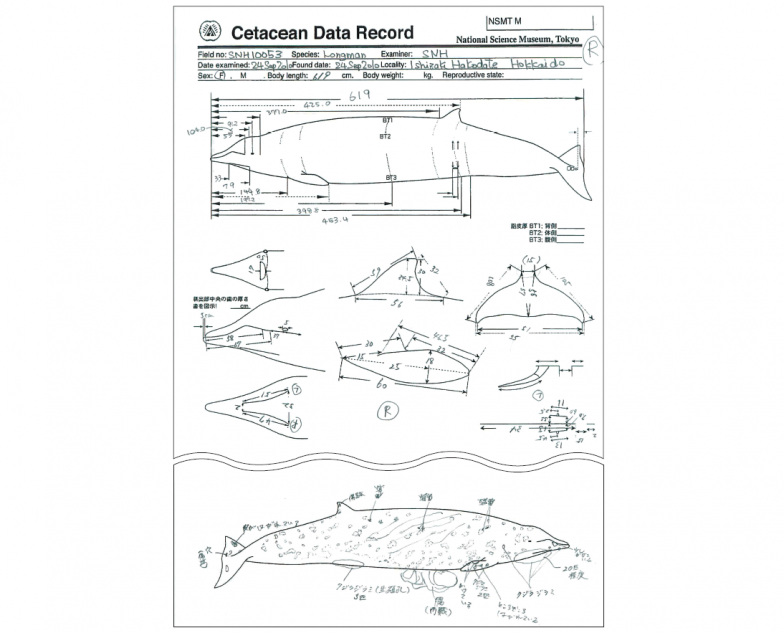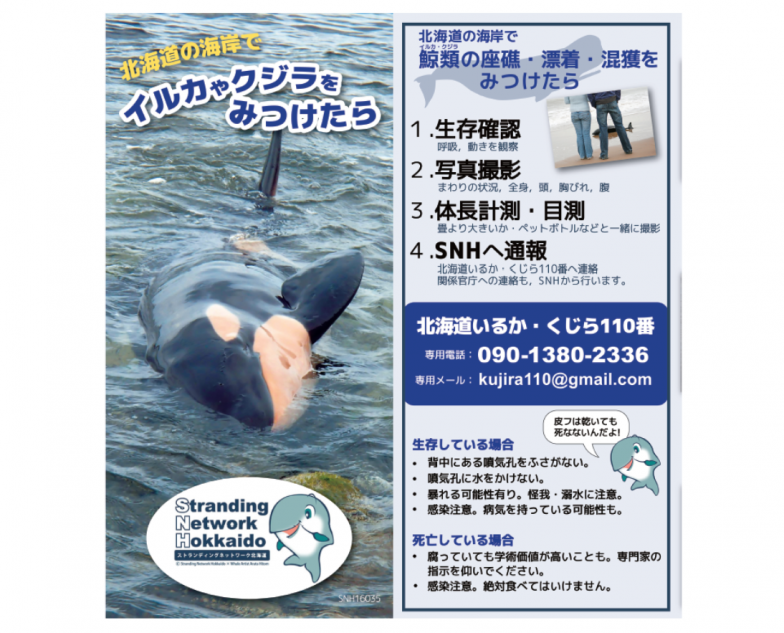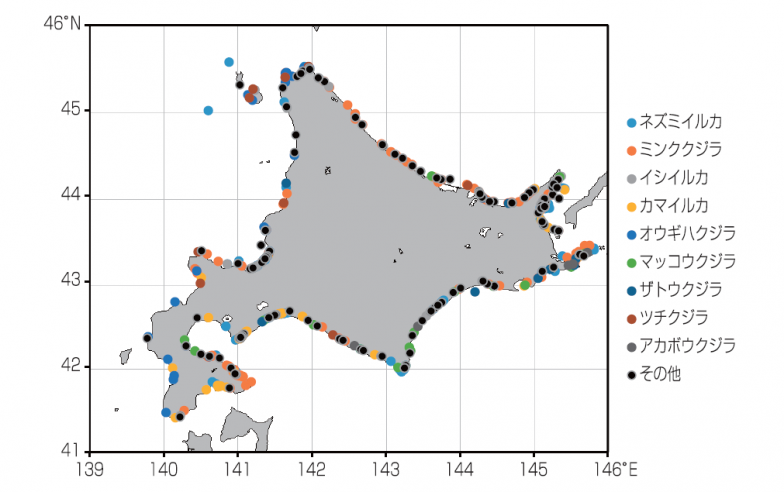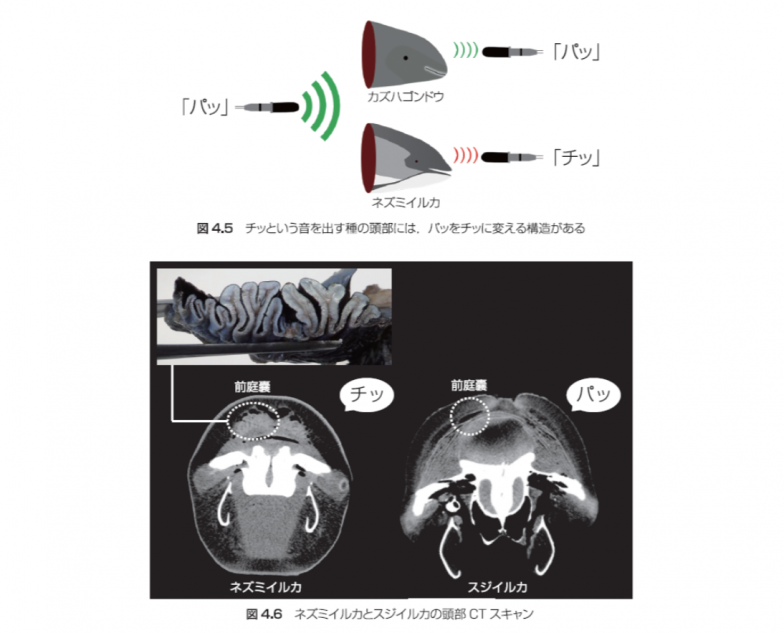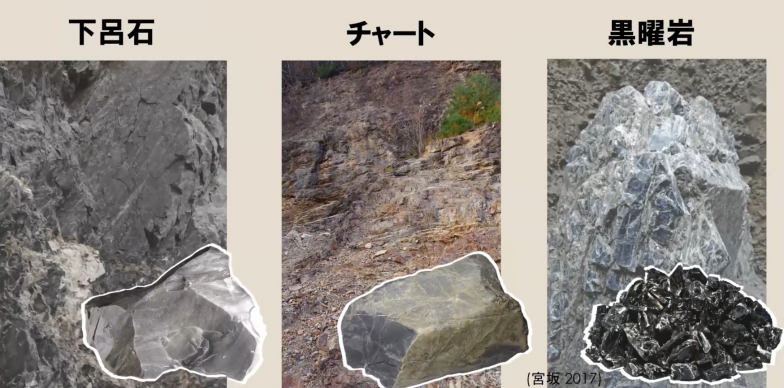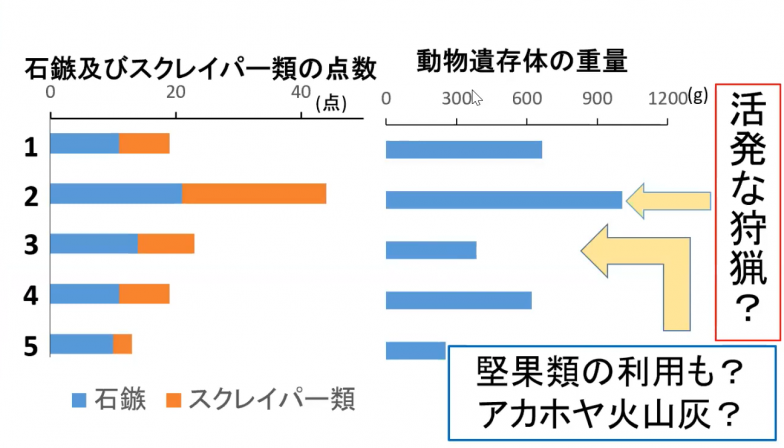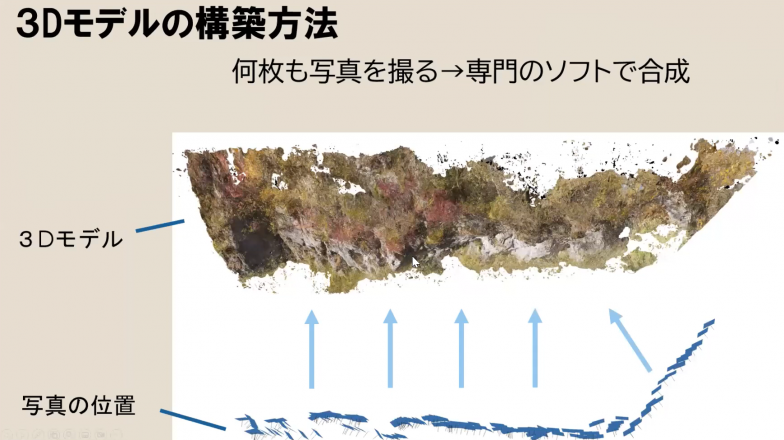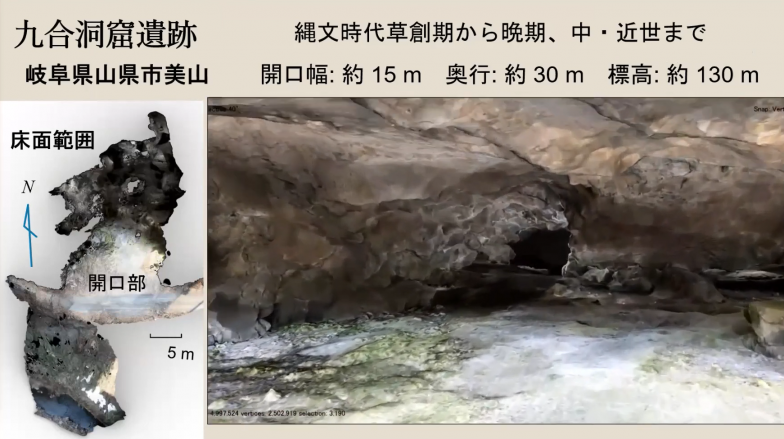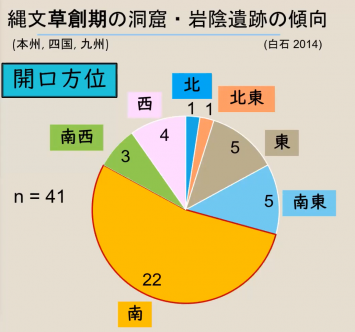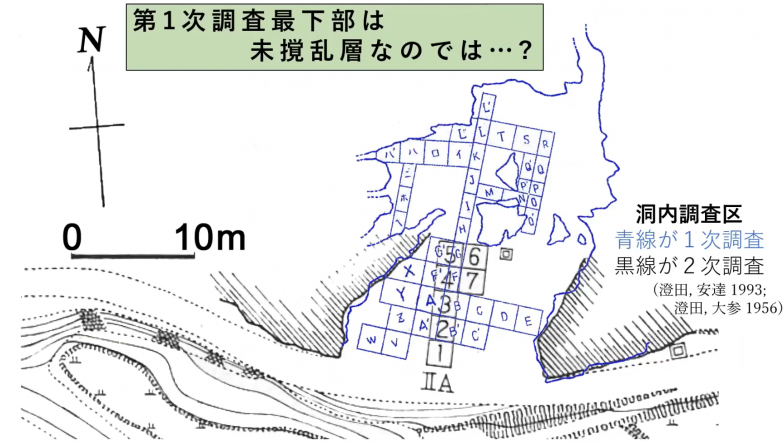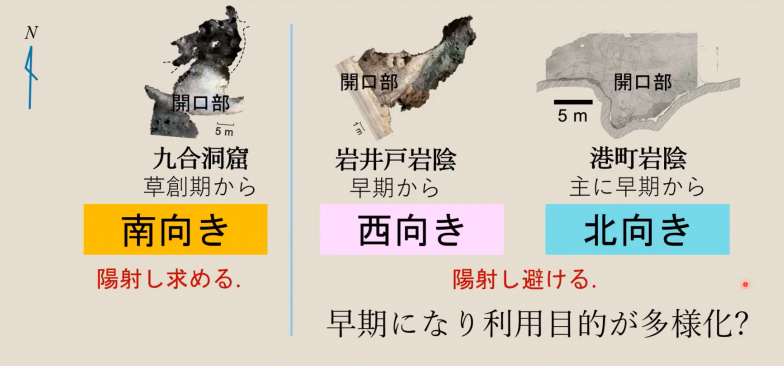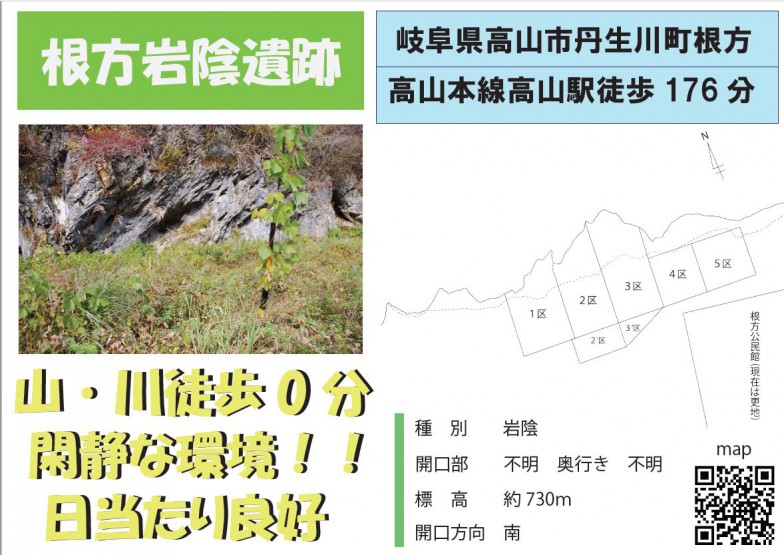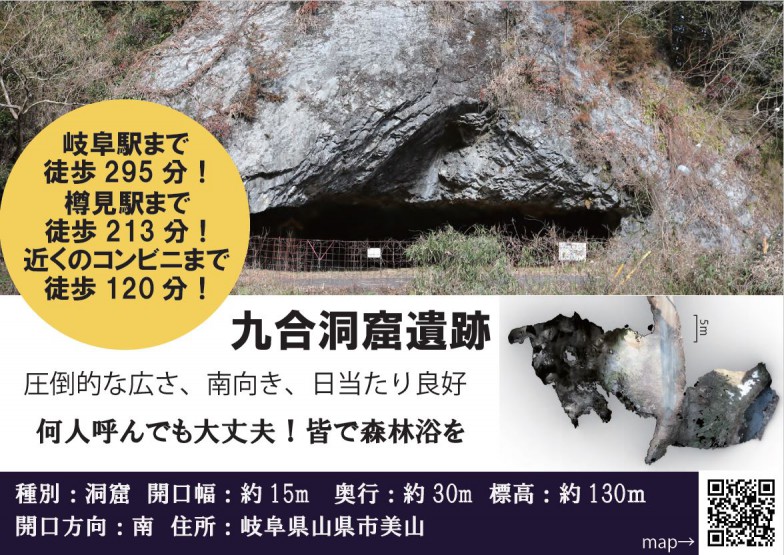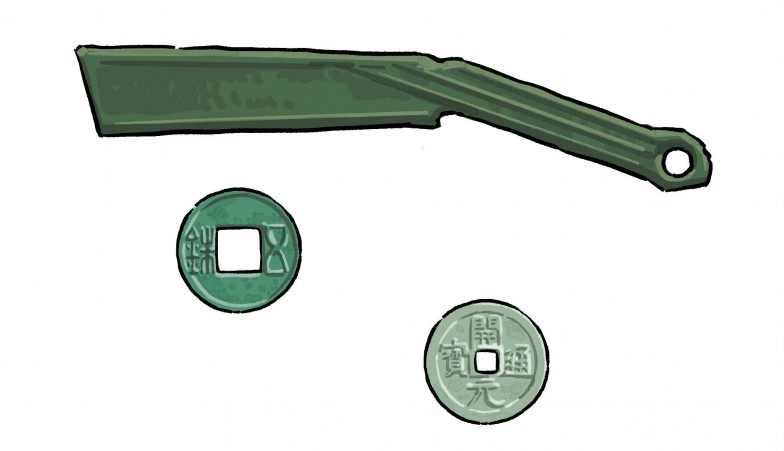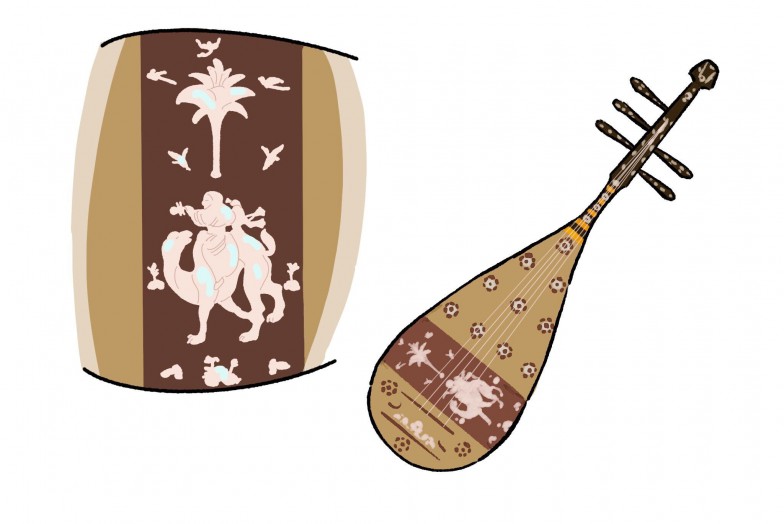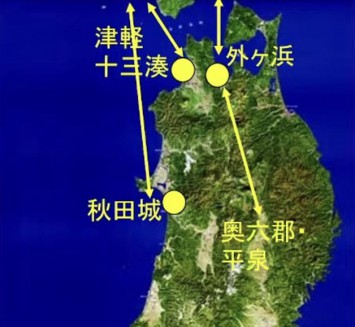自宅のゲルで暮らすモンゴル研究者に聞いた、遊牧社会で生き抜くのに必要な力
2023年9月28日 / 大学の知をのぞく, この研究がスゴい!
家畜の餌となる草を求めて広大な草原を転々とする遊牧民の生活。最近はノマド・ワークなどという言葉が普及するくらい、その場所や人に縛られないイメージは定住生活者を魅了してやまない。
文化人類学者としてモンゴルの遊牧文化を研究する堀田あゆみ先生も遊牧民とその文化に魅了された一人である。研究と実益を兼ねてモンゴルの移動式住居ゲルを自宅の一部として使用しているという。
今回は、なんとそんな堀田先生の自宅ゲルにお招きいただき、専門である遊牧文化のモノの所有についてのお話やゲルのあれこれについて伺ってきた。
住宅地に突如現れる遊牧民の住居・ゲル
7月の中頃、取材のため教えてもらった大阪府内の住所に向かった。場所は日本のどこにでもありそうな古い住宅地で、道は細く複雑だ。だだっ広いモンゴルの草原とはまるで対照的なこの場所で、どんなふうにゲルが登場するのだろう?そんなことを考えながら車を走らせていたら、大きな空き地があるでもなく、民家の軒先に寄り添うように建てられたゲルが現れた。
緩衝地帯があるわけでもない。住宅地にいきなり、ゲル。これはおもしろい。
「民家」の方のインターホンを鳴らし、挨拶もそこそこに上がらせていただく。ゲルを建てるために四角い敷地の縁に沿うようにL字型の木造家屋を建て、中央のスペースにウッドデッキを作ってその上にゲルを設置しているのだという。家からウッドデッキに出る扉を開けると、目の前にゲルの扉がある。堀田先生はこうして、その時の気分や天気によって二つの世界を行ったり来たりしているのだ。
では、われわれもゲルの世界にお邪魔させていただこう。

ウッドデッキに続く扉を開くと、そこにはゲルの入口が!
ゲルとは、モンゴル遊牧民の移動生活に最適化された組立式の住居である。
移動を頻繁に繰り返すゲルの構造で重視されるのは、軽さと組み立て・解体の容易さだ。カラマツの木で作った部材を格子状に組んだ壁と天窓から放射状に組まれた屋根棒、さらに真ん中で屋根を支える2本の柱。釘は使わず、部材同士を紐で結んで組み上げる。壁と屋根を羊毛フェルトで覆い、最後に外側に白い布をかぶせて紐で固定したら完成である。慣れると大人3~4人で、設営に2時間、解体に1時間くらいしかかからないらしい。
夏は壁の覆いとフェルトをまくり上げて風通しよくすることで涼しく、冬は地面と接する部分に盛土をして気密性を高めることで暖かく過ごせる優れものだ。丸い形は風を受け流すのに最適で、軽量ながら強風に吹き飛ばされるということもまずない。

ゲルには「部屋割り」というものは存在しないが、場所によって役割分担はある。一番奥(入り口から見て反対側)はホイモルといって、ゲルの中で一番大切な場所だ。通常は仏壇や家族写真など、家族以外の人に見せたいものが置かれている。

そして入り口から見て左側は男性のスペース、右側が女性のスペースだ。客人がきたときの対応は男性側、家事は女性側で行われる。

雨が少ないモンゴルでは、採光と風通しのため夏の日中はゲルの天窓はほぼ開けっぱなしだ。天窓から下がっている赤い紐は、強風が吹いた時に重しを吊るしたり、家族総出で掴まってゲルが吹き飛ばされないようにするために使用される。
このように、モンゴルの気候と移動を繰り返す遊牧民の生活に最適化されたのがゲルなのである。気になる日本の風土にマッチするのかどうかについて堀田先生に聞いてみたところ……ずばり「向いていない」とのこと。モンゴルで使われているものをそのまま持ってくると、やはり雨の多さや湿度の高さが致命的であっという間に腐食が進んでしまうらしい。
そこで、モンゴルで調達した部材を使いつつ、フェルトを諦め、さらに外側の布を防水シートに交換している。土の上にじかに設置しないのも湿気対策の一環だ。
「設置しっぱなし」もよくないので定期的に解体と設営をしている。堀田先生曰く「一箇所に留まることを退廃とみなす」という遊牧民の価値観をそのまま反映した住居がゲルなのだ。
たいへんである。よほどのゲル愛、モンゴル愛がなければここまでできまい。
ゲルから「家屋」の方に戻った我々(日本の7月のゲルの中は蒸し暑いのだ)は、まずモンゴルに情熱をかけ、研究までするようになったきっかけを聞いてみることにした。
きっかけは「自然と人間の共生」
「私は子どもの頃『人間と自然の共生のバランス』を探ることに関心がありました。どこまでなら共生でどこからが搾取なのか、みたいなことをもやもやと考えてたんですが、その頃たまたま遊牧民の生活について知って興味を持ったんですね。
モンゴルに関する本をいろいろ読んでいると、遊牧民の生活は自然と共生していて、しかも彼らはモノにあまり執着しないということが書いてあったんです。
どうやったらそんな境地に至れるんだろう? 同じ人間なのに…と、衝撃を受けるのと同時に、『自然と人間の共生』のヒントがここにあるんじゃないかと感じました」
モンゴルに関心をもった堀田先生は高校卒業後にモンゴル語を学ぶための留学をした。モンゴルの首都ウランバートルでホームステイするうちに、そこで見た光景に違和感を覚えたという。
「話を聞くためには言葉がわからないとダメだろうと思い語学留学をしました。そのときは遊牧民的な草原の生活はできなくてウランバートルのアパートでホームステイをしたんですが、不法投棄されたゴミが目立つのが気になったんです。またアパート地区の周りには地方から移住してきた人たちがゲルで暮らす地区があったんですが、そのゲル地区でゴミの野焼きが原因の大気や土壌の汚染が問題になり始めた時期でもありました。そういったものを見ていて、どうも本で読んだ話と違うなあと感じ始めたんです」

遊牧地域におけるゴミ処分の様子。
「帰国後は大学に進学して『ウランバートルの廃棄物処理システム』について調べ、修士課程では『住民の環境意識』をテーマにしました。そしてその過程で根本的な疑問を抱きました。
当時日本のJICA(国際協力機構)やその他の国際機関がモンゴルのゴミ処理システムを改善する事業をしていましたが、ゴミとか廃棄物というもののとらえ方が我々とモンゴル人ではたして同じなのかと。都市で生活しているとはいえ数世代前までは草原で遊牧をしていた人々なので、ゴミに対する認識にも遊牧民の価値観が反映されているのではないかと考えたんです。
そしてゴミについての認識を知るためにはまずモノについての認識を知らなければなりません。ゴミというのはモノが最終的に行きつく形態ですから。そこで、博士課程の研究で今日まで続く『モンゴル遊牧民の物質文化』というテーマをやることにしたんです」
「遊牧民はモノに執着しない」は幻想!?

ゲルでの住み込み調査(2016年2月)
遊牧民はモノをどう捉えているのか?
そんなテーマで研究を始めた堀田先生だが、実際にゲルの中で遊牧民とともに生活しはじめると彼らのモノに対する並々ならぬ執着に圧倒されっぱなしであったという。
「遊牧民のモノに関する研究というのはこれまでにもあるんですが、それらはモノの量に注目したものが主流でした。たしかに彼らの持ち物は日本人に比べれば少ないですし、今風に言うとミニマリスト的理想を実践しているように見えるかもしれません。それゆえ『遊牧民は頻繁に移動するので最小限のもので暮らしていて家具も簡素である』という、彼ら自身がモノを持たないことに価値を見出しているかのような解釈が付与され続けてきたんです。
かくいう私も調査地に入るまではそういう話を信じていたので、実際にゲルで暮らし始めてからは周囲の人たちの私の持ち物に対する関心の高さに驚きましたね。
例を上げると、スーツケースを開けて中身をいじってたら背後から音もなく近づいてきて中に何が入っているのか覗き込んでいたということがありました。隣のゲルのおばさんが私のブーツをやたらほめてくれるなと思ったら、おもむろに試着を始めて『うーん、私の足にぴったり。あゆみは裸足で帰ることになるわね』と言われたことも。ほかにも、こちらの着ているTシャツを指して『そのTシャツ初めて見た!うちに置いてく?』と聞いてきたり。
事例を上げたらキリがないですが、このままだと身ぐるみはがされる!と思うくらい彼らのモノに対する関心の高さには圧倒されました」
こちらが持っているモノについて知りたい、譲ってほしいという周囲からの圧力がすごかったと。
「慣れるまではたしかにたいへんでしたが、しばらくすると彼らと我々ではモノやその所有に対する考え方、執着のあり方が根本的に違うんだということがわかってきました。
日本人の言うモノへの執着って、対象の占有を問題にしていると思うんですね。所有者の手元にそのモノがあるということが重視されるのが我々農耕タイプの社会だとすると、所有と占有が必ずしも結びついていないのが遊牧社会だと言えます。
遊牧社会でももちろん所有権は存在しますが、その一方で貸借か譲渡かをはっきりさせない『融通』が頻繁に発生します。これはあるモノを必要とする人がそれを持っている人のところに行き、交渉によって渡してもらうことなんですが、すぐに返却するのか、督促されるまで返さないのか、あるいは返却しないのかは当事者間の関係性や対象のモノによってケースバイケースです。
そもそも遊牧民はモノを交渉によって人の手から手へ移っていくフローとみなしています。そこで重要なのは所有者が誰なのかということではなく、必要になったときにそのモノが利用できるということなんですね。なので、遊牧民はモノの所有には執着しませんが、ことモノの利用ということになると並々ならぬ執着心を見せます」
なるほど……、我々日本人からするといまいちピンとこない価値観かもしれないが、ところ変われば常識も変わるというもの。しかしこの常識の存在に気づいてから、前述の持ち物に対する関心の強さについても腑に落ちたという。
遊牧社会で生き抜くために必要なもの、それは情報収集と交渉の力
「私が最初『身ぐるみを剥がされる!』と感じたくらいの持ち物への関心、あれはつまり交渉だったんです。日本人の感覚だと交渉というのはする側もされる側もそれなりの覚悟が必要だと思いますが、モンゴル人の交渉は本当にカジュアルで、ほとんど『とりあえず言ってみた』の延長です。そのやり方も、可愛くおねだりや泣き落としから高圧的なものまで相手やモノによってさまざまです。とはいえ、そういったスキルが一朝一夕で身につくわけではないのも事実です。モンゴルの子供たちは、自分の要求を相手に伝え、どういう条件を提示すれば上手くいくかということを実践形式で学んで育ちます。
で、面白いのが、こういったモノをめぐる交渉というのがモンゴル帝国時代から行われていたってことなんですよ。13世紀の半ばに帝国を訪れたフランスの修道士もモノをせがまれた様子をしっかりと記録してます。
そして、交渉スキルと同じくらい大切になってくるのが情報収集の力ですね。厳しい自然の中で生きる遊牧生活には臨機応変な判断力とそのための情報を集める力がそもそも必要不可欠です。例えば日中にゲルの扉を開けっぱなしにしておくのも、室内にいながら外でされる会話や人の行き来を把握しておくためです」

日中は開けっぱなしにされるというゲルの扉。風に乗って聞こえてくる外の会話は貴重な情報だ。さらに馬や車に乗って移動する音が聞こえてくれば、音の移動する方向やエンジン音の特徴などから誰がどこへ向かったのかがわかることもあるんだとか。まるで潜水艦のソナーのように、室内にいながら外部の情報をもたらしてくれる窓口、それがゲルの扉なのである。
「情報が大切なのはモノを巡る交渉でも同じです。交渉のスタート地点は『誰のところに何があるか』という情報を得ることなので、機会さえあれば相手がなにを持っているのかを探ろうとしますし、逆に絶対に人に渡したくないものについては隠すという情報管理も行われます。
ここで話が最初に戻るんですが、ゴミの野焼きが問題になっているという話がありました。あれも、じつは情報管理の延長にある習慣だったんじゃないかと思うんです。捨てるだけならべつに燃やす必要はないはずです。なのにそんなことをするのは、そのまま放置すると断片的とはいえ自分たちの持ち物についての情報を晒してしまうことになるからじゃないかと。他人に拾われたり情報を晒すことを完璧に防ぐには燃やすという行為が必要だったんじゃないかと思うんです。ガラスや金属のような燃やせないものが増えた現代ではそれが環境問題につながっているわけですが」
話がつながった。
ゲルは人が集まる場所
最後に、ふたたびゲルの中に入って羊のくるぶしの骨を使ったモンゴルの遊びを教えてもらった。

モンゴル語でシャガイという羊のくるぶしの骨を使う。

床に転がし、上を向いた面によって「羊」「山羊」「馬」「ラクダ」という目が割り当てられる。おはじきみたいにしてルールにそってぶつけ合って遊ぶのだ。
ゲルを建ててから、人がやってくる機会が増えたと堀田先生は言う。訪問者は興味本位で「これはなんですか?」と聞いてくる人から、解体・設営を手伝ってくれる人までさまざまだ。
もともと遊牧民は自分のゲルにやってきた人を拒むということをしない。だから、自分以外に誰もいない草原で地平線にゲルを見つけた時の安心感はひとしおなのだ。そういう場所を日本にも作りたいと考えたのが、ゲルを建てた動機でもあるのだそうだ。
既製品を使わず、知り合いの遊牧民に材料から見立ててもらった思い入れ抜群のゲル。今はそこに新たなライフヒストリーが蓄積されていくことが、モノをテーマにした研究者としてうれしい毎日なのだそうである。