「アジア人文学」をテーマにした全学シンポジウムは、新たなフェーズへ
産学連携といえば「理系」というのはもう古い、これからは「文系」が活躍する時代だという思いを強くするシンポジウムが開催された。京都大学の人社未来形発信ユニットがシリーズで開催している「アジア人文学」をテーマにした全学シンポジウムの第3回目「アジア人文学と産学連携」である。(第1回全学シンポジウムのレポートはこちら、第2回全学シンポジウムのレポートはこちら)
最近、「Society 5.0」という言葉をよく耳にするようになった。これは仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会課題の解決をはかる人間中心の社会だとされている。生活が便利で豊かになった一方で、エネルギーや食糧の問題、高齢化、国際競争や経済格差など、社会の課題は複雑化していくばかりだ。IoT、AI、ビッグデータなどの技術で今までになかった価値を生みだし、これら課題や困難を克服する社会イノベーションを図ろうというのがSociety 5.0の基本的な考え方になる。
このSociety 5.0に代表されるような「高度情報技術を基盤とした未来社会」のデザインと実現をめざすうえで、最先端技術の社会実装に取り組む企業の技術者と、人や社会のあり方を探究する人文・社会科学系の研究者との共同研究の重要性が増してきている。京都大学では、このための共同研究プロジェクトを、日本電信電話株式会社(以下、NTT)や株式会社日立製作所(以下、日立)とともに取り組んでいる。考えてみれば、人間社会の課題を解決し、人の暮らしや生き方、社会のあり方をよくするための技術開発に、人文・社会科学の知は不可欠である。今回のシンポジウムは、この共同研究の当事者たちが、プロジェクトの現状と未来展望について発表、議論する場となった。

開会の挨拶を述べる、人社未来形発信ユニット長の出口康夫先生
よりよい人生や社会のあり方を提案する技術
第一部の基調報告では、NTT、日立、京都大学それぞれから共同研究の目的やそれに向けた期待が語られた。
NTTは、「IOWN」というインターネットを越える新たなネットワーク構想を発表している。ここでは電気信号を使わない光による演算システムによって、超々低消費電力で効率も速度も桁違いのオール光によるネットワークを実現。これにより、遠隔診療、防災、教育、自動運転、金融、エンタテインメント、スポーツ、製造など、あらゆる分野でモノや人のやり取りの再現や試行が可能になるのだという。
登壇した代表取締役社長・澤田純氏は、「人格や付き合いなどもサイバー空間の中に再現され、再現された客体同士が、情報を交換したりシェアしたり、学習したりする複雑な関係を構築する世界がつくられる」という。このようなまったく新しいコミュニケーション環境では、自己と他者との関係やリアルとバーチャルとの境界など、さまざまな面で人々の不安やストレスが予想される。そこで、技術の進化が人と調和するための新しい世界観の構築、生きがいや倫理観、社会制度などを人文・社会科学の研究者と一緒に検討したいと、2019年10月から京大との共同研究をはじめたのだと語った。

京大との共同研究プロジェクトの意図を語る、澤田純氏
一方、日立は、2016年から京都大学との連携をスタートしている。「日立京大ラボ」を開設して京都大学内にスタッフが常駐。霊長類、税制論、古代ローマ史、人のこころのありよう、東南アジアやアフリカの社会など、さまざまな分野の研究者と対話を重ねて2050年までの未来の課題を探索している。
見えてきたのは、未来、国家、労働の喪失によって生じる根本的な問題、「信じるものがない、頼るものがない、やることがない」という危機。危機脱出の糸口としたのは、人々が主体的に課題解決に参加する社会イノベーションのあり方である。これら対話を踏まえ、生物に学ぶ社会システム、政策提言AIなど、社会イノベーションにつながる基礎技術や学理について研究を進めている。執行役常務CTO兼研究開発グループ長兼コーポレートベンチャリング室長・鈴木教洋氏は、従来型の産学共同研究が「限られた分野で技術的なゴールをめざし、確立されたプロセスを推進するもの」であるのに対して、不確実な時代の産学連携のゴールは「価値創造」であり「サスティナブルな社会の仕掛けの創出」だと語った。

これからの産学連携の役割について話す、鈴木教洋氏
これらを受けて京都大学人社未来形発信ユニット長である出口康夫教授が、人文・社会科学系の知を活用してもらうことで、産業界の文化資本力、コンセプト発信力が強化できると話す。同時に、人文知、とくに哲学にとって産学連携は、衰えてきた俯瞰力や提案力を身につけるきっかけになると提起した。
どの報告でも明確に示されたのは、これからの技術は、よりよい人生や社会のあり方を提案していくものでなければならないということだ。誰も置いてきぼりにしない、あたたかみのあるイノベーションが実現されるのではないかと、強い期待を感じた。
IT基盤・デジタル技術の研究から「社会づくり」の研究へ
第二部の研究成果および展望では、さまざまな興味深いアプローチや成果が報告された。その中から少し取り上げてみよう。
NTTの渡邊淳司氏は、情報の今までにないあり方を見せてくれた。受け手がどのような意味を受け取るか、他者との関わりのなかで生じる価値に着目。「触覚」によって情動や行動に変化が生じる装置や場を研究している。
たとえば、普段は触れることのできない心臓の鼓動を手の上の触覚として感じる「心臓ピクニック」ワークショップ。自分の鼓動に触れることは自律神経のリラックスした状態につながるそうだ。また、目の見えない人と一緒に楽しむスポーツ観戦として、たとえば柔道の選手になりきって手拭いを引っ張り合うことで動きや勢いを表現して、試合を翻訳する試みなども紹介された。「身体に働きかけあう体現の場は、感覚や身体の違いを超えた、新しい人と人のつながり方を生み出す」と、渡邊氏はいう。

ユニークな発想で研究を推進する渡邊淳司氏は、著書も執筆している
日立京大ラボ長である日立の水野弘之氏は、日立京大ラボでの産学連携は、IT基盤・デジタル技術の研究から社会づくり・社会改革そのものの研究へと変化してきていると語る。技術者がともすれば技術オリエンティッドになってしまうのに、人文・社会系の研究者が待ったをかけ、よりよい社会への技術転用への可能性を示唆してくれるという。「ラボではよく、人社系の研究者から『そもそもこの処方箋は何? 何のために何をしようとしている? どうすればよりよい処方箋になる?』 という突っ込みが発せられる」と、水野氏は話す。いかにも人文・社会系の研究者が言いそうなフレーズ、共同研究の風景が脳裏によぎった。
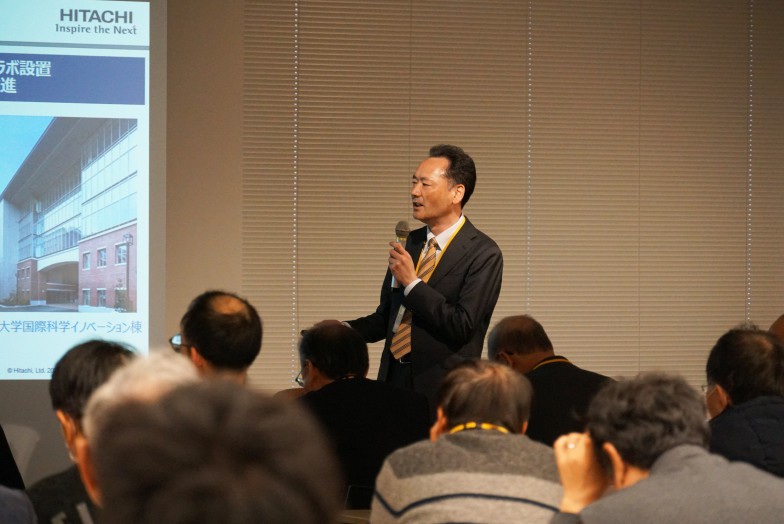
日立京大ラボ長である水野弘之氏は、京大との共同研究での気づきを語った
京都大学こころの未来研究センターの広井良典教授は、日立京大ラボとの共同研究によるAIを活用した社会構想と政策提言について報告した。その方法は、これからの社会を考えるうえで重要な約150の指標を立てて因果関係をモデル化し、指標間の結びつきの強さや時間のずれを数値化。出てきた約2万通りのシナリオを、人の目で価値判断を行って分類していくというものだ。結果は、都市集中型か地方分散型かが大きな分岐点となり地方分散型が望ましいと出た。しかし、運用には細心の注意が必要であることもわかったという。
実際に、このシステムを使った政策提言を長野県で行ったところ、「AIにはできない人間固有の領域が明らかになりました。どういう社会をめざしていくのか、何をもってよい社会と考えるのかは、人間固有の領域なのです」と広井先生は説明してくれた。

広井良典教授は、日立と取り組んだ長野県の政策研究について発表した
発想が変わるから社会が変わる
第三部では、産学連携、そして提案すべき価値観であるウェルビーイング(身体的、精神的、社会的に良好な状態であること)やハピネスをキーワードに、登壇者全員によるディスカッションが行われた。
産学連携の効果を端的に表現したのは鈴木氏。研究者自身のマインドが「テクノロジー発想から社会的な価値に基づいて何をやらなければならないかという発想に変わった」という。客席から参加した日立京大ラボ主任研究員の工藤泰幸氏も、「社会がどうなっていて、その社会のためにどういう技術をこれからつくればいいのかを考えるようになった」と話す。
東京大学人文社会系研究科・唐沢かおり教授は、人文学には、人間、社会について考え、社会実験をやってきた知識の集約があると話し、産学連携しやすい哲学、心理学、社会学だけでなく文学や歴史学なども含めて総体を巻き込む必要性を示唆。人文・社会知の時空間の広がりがわかるマップを、企業の人々も使えるようになるための対話の場を提案した。賛同したのは、工藤氏と同じく客席から指名された歴史学が専門の京都大学大学院文学研究科の南川高志教授だ。言説そのものには意味はなくても、歴史で裏付けされると途端に実体を帯びてしまうという歴史学の怖さに言及。人文学を総合して一つの力にしていくことで、貢献する力がアップすると述べた。
歴史と時空間の広がりを産学連携の中にどう入れ込めるかに興味があると話すのは澤田氏だった。NTTが提唱する新しい情報通信社会基盤がどんな世界を実現していくのか、先人に学び、技術に制限をかけたり技術開発の方向性をガイドするものが必要であり、人文・社会科学には、社会のウェルビーイングをどうしていくかという視点での示唆を期待しているという。また、京都大学大学院経済学研究科・坂出健准教授は、社会の価値観と個人の主観的なウェルビーイングは相関するとし、それを伝える制度、民主主義という制度が本当に望ましいかを考えていく必要があると述べた。

ディスカッションは、意見が意見を呼び白熱した
すでにポストAIを考える時期に
客席からの質問に答え、AIの発達もテーマになった。AIで仕事が奪われるのではなく種類が変わるだけだと水野氏。キャンプに行ったら一日中ご飯をつくっていなければならないが、昔はそれが日常だった。仕事がなくなることは本来いいことだが、やることがなくなると、人間はなぜ生きているのかを考えてしまう。そこに対して解を与えるのは、人文・社会科学の知見ではないかという。
唐沢先生は、AIを使ってこういう社会をつくりたいという、ビジョンを持つことを重要視する。一気に広まる危険性も十分にある時代なので、責任の概念をどう捉え、法体系がどう支え、われわれがどう受容するのかという統合的な議論を繰り返し、AIが普及した社会を描いたうえで、進めていくことが大切だと述べた。
科学史が専門の広井先生は、物質、エネルギー、情報と発達してきた科学の歴史を長いスパンで見てみると、情報技術はすでに成熟段階を迎えており、ポストAIを考える時期にさしかかっていると主張する。ポストAI・ポスト情報は「生命」で、分子生物学的な意味だけでなく、人生、生活、地球の生態系、サスティナビリティも含めた概念であり、情報やAIとも結びついていくと、広井先生は予測する。こういった展望について、人文・社会科学の研究者と企業とが議論しながら考えていくべきだと、先生は期待を語った。
このレポートは、もっとさまざまな議論が展開されたうちの一部に過ぎないが、この盛りだくさんな感じ、わかっていただけるだろうか。この豊かな議論が、産学連携の価値なのだろう。私個人は、「技術よ、どこまでいくんだ」と嘆息したり、農業では大変な作業でもみんなで取り組むのは収穫の時期=未来を信じているからであり、未来を信じられるからこそ生かされている喜びを感じるのではないかという発言に少し安心したり、結構忙しかった。文理共創の一端に触れ、話して聞いて考える営みの迫力を実感した、密度の濃い4時間半だった。

4時間半の長丁場だったが、多くの人が最後まで聞き入る、濃密なシンポジウムだった
