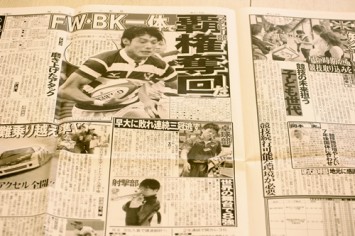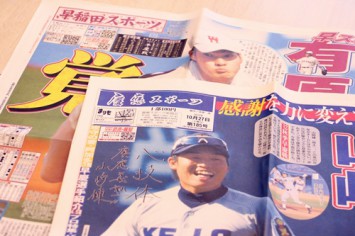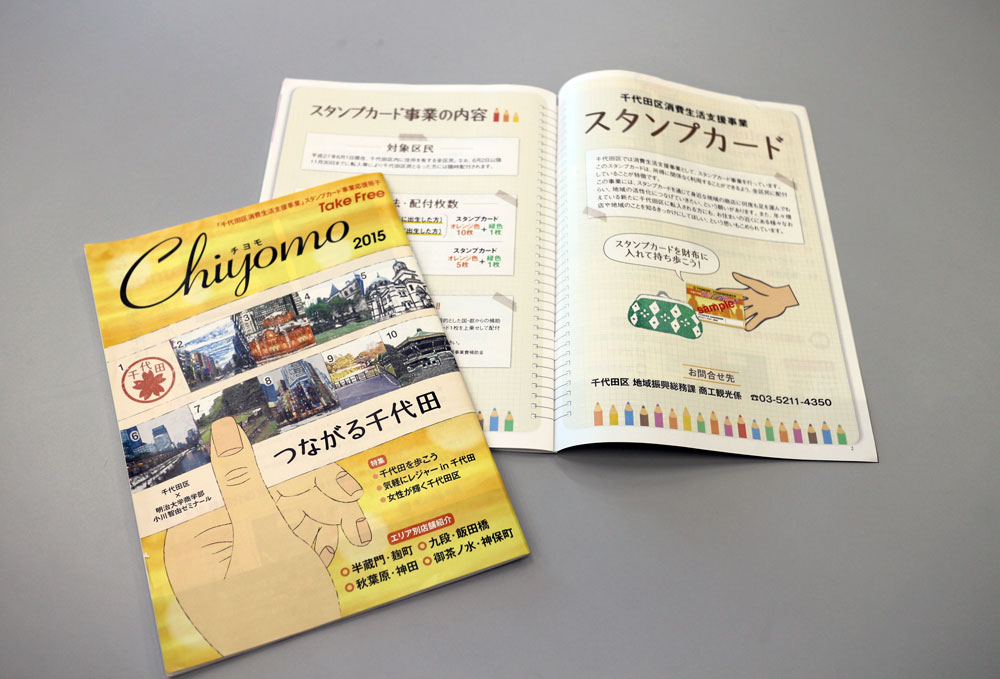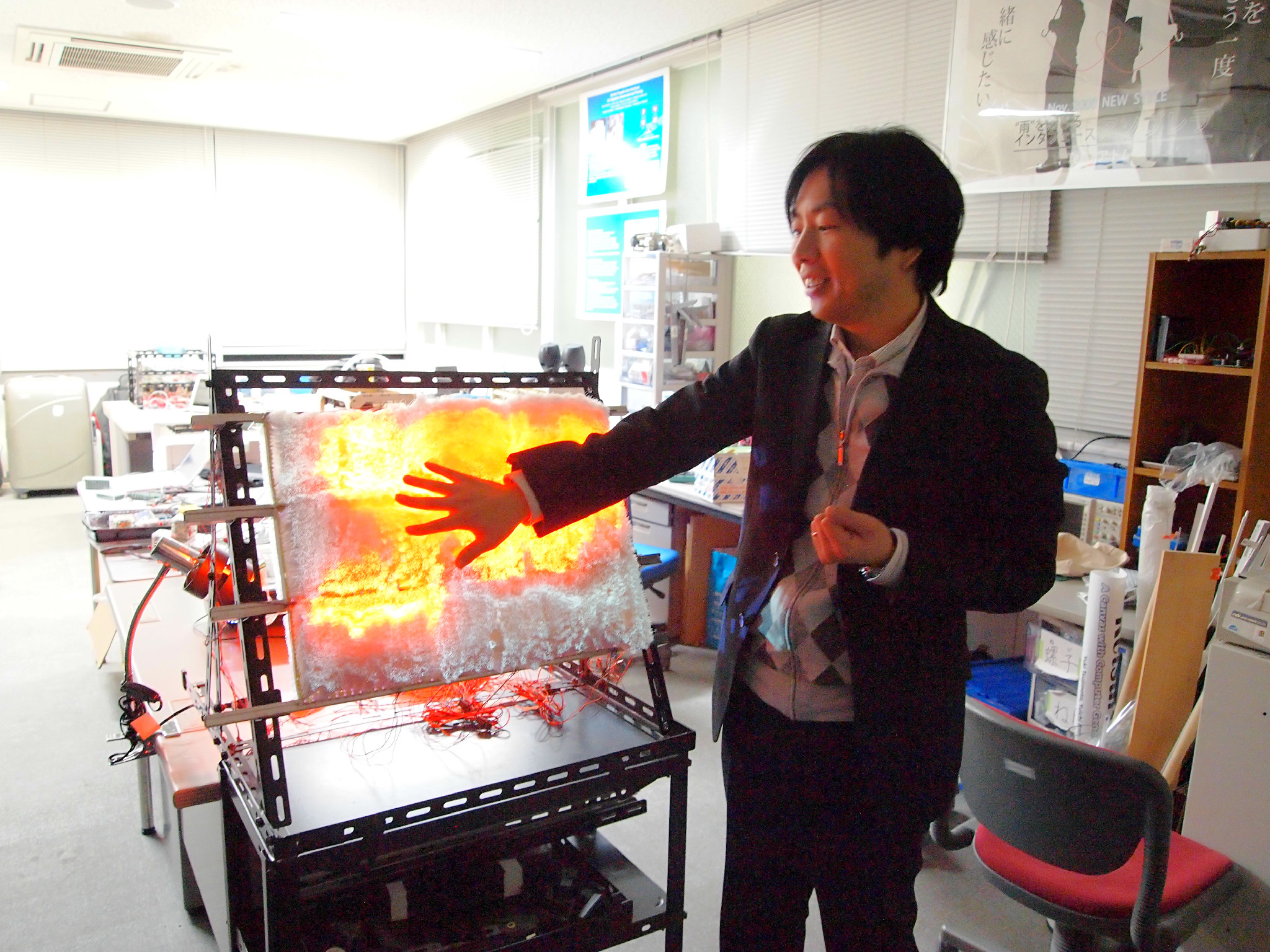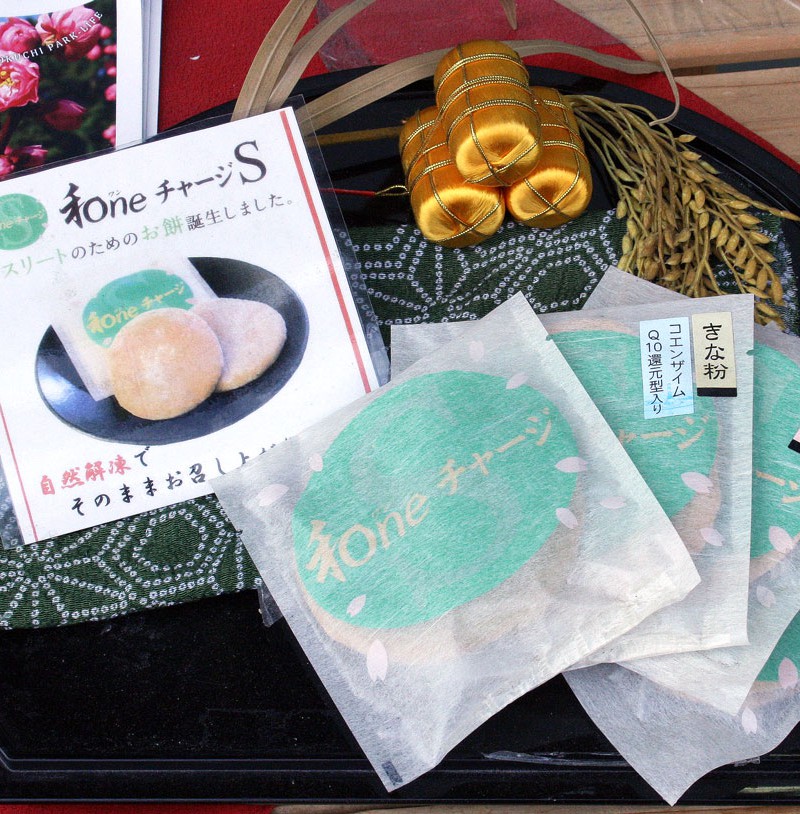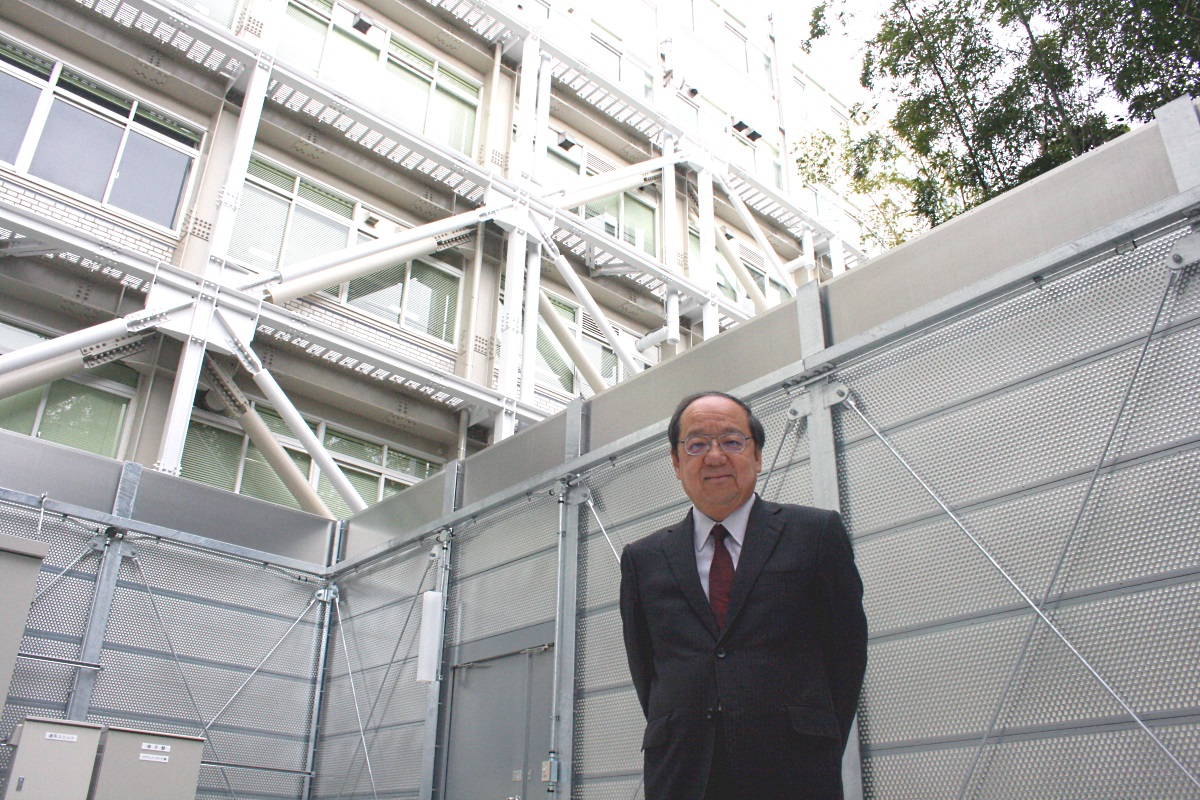大学×地域の本気を見た「いばらき×立命館DAY」体験レポート
さわやかな風、真っ青な空、こんな気持ちのいい日曜日に、家でゴロゴロしていてはお天道さまに申し訳ない。そんなことを思ってか、思わないでか、行ってきました! 立命館大学と大阪府茨木市による地域交流フェスタ「出会う、つながる、つくりだす いばらき×立命館DAY 2017」!当日の来場者はなんと約10,000人!大学祭とはまた違う、大学と地域が手を取り合ったイベントの底力を垣間見た。
JR茨木駅から歩くこと約5分。まちとキャンパスの間に塀が存在しない、立命館大学の「大阪いばらきキャンパス」が今回の舞台である。入り口こそ人がまばらだったが、会場付近に行くと人、人、人。親子連れを中心に、たくさんの人で埋め尽くされていた。

会場のメインストリートには人がいっぱい
会場でひときわ目についたのは、巨大な茨木童子のバルーンハウスだ。ちなみに、茨木童子は茨木生まれの鬼で、かの有名な日本妖怪界のプリンス(?)、酒呑童子の第一の子分とのこと。とはいえバルーンハウスには、鬼の怖さなんてなく、かわいい姿で子どもたちに大人気。長蛇の列がつくられていた。

遠くからでも目につく、インパクト大の茨木童子
そして、茨木童子を横目にずんずん進むと、メインステージである空のプラザと、さまざまな飲食店のブースが並ぶ会場の中心地。大学祭の場合、飲食店のブースは学生たちが運営するのだが、今回は地域交流フェスタ。立命館が関係するブースともに、茨木市界隈の人気店が多数出店しており、どれも美味しそうで目移りしてしまう。
私が食べたのは「茨木バニラホップソフト」という、開発に立命館も関わった茨木のご当地ソフトクリーム。ホップの苦みとさわやかさがほのかに感じられる味は、今日のような暑い日にピッタリ。こいつはちょっとした逸品である。

さわやかな味わいがクセになる「茨木バニラホップソフト」
そしてソフトクリームを食べていたら、空のプラザから音楽が。あわてて行ってみると、学生たちの「よさこい」がはじまっていた。プログラムを見ると、ここではよさこいだけでなく、マジック、社交ダンス、チンドン屋などなど。一日中さまざまなプログラムが開催されているとのこと。ちなみに、学生たちのパフォーマンスは、キレッキレで見応え◎ 続くアカペラサークルのコンサートも非常によく、ひさびさに聴く、槇原敬之の『どんなときも』にしみじみしてしまった。

よさこいサークル「京炎そでふれ! おどりっつ」

アカペラサークル「Empire Cast」
このイベントのおもしろいのは、学生による屋台やパフォーマンスといった、いわゆる大学祭的な催しだけではないところである。茨木市による相談ブースをはじめ、市民向けの啓発活動を行う展示や講座であったり、ソフトバンクや無印良品など大阪いばらきキャンパス付近に店舗をもつ企業や市民団体のブースもあったりする。これらブースが集まるイベントホールで、ひときわ目についたのは、立命館大学の鉄道研究会によるプラレールの大規模展示だ。食い入るように、子どもたちが見ていたのが印象的だった。

鉄道研究会のプラレールは、子どもたちに大人気

アンケートに答えて産学連携商品「ソイデリ」もゲットしたゾ
このほかにも立命館大学クラブチームによるスポーツ体験教室や、プロの芸人さんによるお笑いライブ、古本市などなど。見どころをあげればキリがない。大学らしさが存分に出ているものの、大学だけではできないプログラムの幅広さが、本当に魅力的だった。そして、何よりもよかったのは、たくさんの子どもたちの笑顔である。こんなにたくさんの子どもがいて、楽しそうにしている大学のキャンパスというのは、今までお目にかかったことがない。ちょっと大げさかもしれないが、大学の“これから”を感じさせるような、そんなイベントだった。
今年のイベントは終わってしまったが、毎年5月に開催しているので、興味がある人はぜひ来年、足を運んでみてほしい。ほとゼロのイベントカレンダーでも告知するはずなので、こっちもチェックだ!